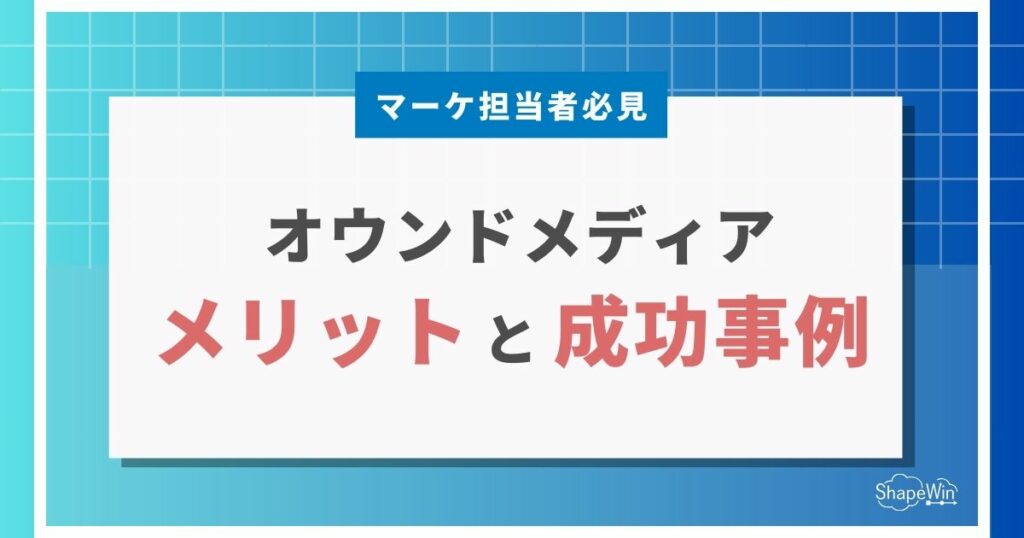広告費は年々高騰し、SNSの流行も目まぐるしく変化する中、長期的な効果を発揮する集客手法として「オウンドメディア」が注目されています。
しかし、「自社メディアにコンテンツを投稿するだけで良いのか」「本当に効果はあるのか」と疑問を持つマーケティング担当者も多いでしょう。
また、オウンドメディアの運営にあたっては、自社にとっては当たり前の知見が、外部からは貴重な情報資産になることに気づきにくいという課題も存在します。
本記事では、オウンドメディアが企業にもたらす6つの具体的なメリットと、押さえておくべき課題、さらには、寄稿記事やSNS投稿など様々な形で再利用できるコンテンツ資産の作り方まで、成功事例も交えながらお伝えします。
オウンドメディア特有の強み

オウンドメディアとは、企業が自社で保有するメディアの総称であり、他のメディアと比較して特有の強みを持っています。
その核となる特徴は、「コンテンツの自由度の高さ」と「資産性」です。これらの特徴を活かすことで、持続的な集客やブランディングの効果を最大化することができます。
まずは、この2つの特徴を押さえましょう。
関連記事:広報PRで必要な3つのメディアとは?〜アーンド・オウンド・ペイドの違いは?
発信内容を自由に決定・変更できる
オウンドメディアの最大の特徴は、コンテンツの発信内容を企業が自由に決定・変更できる点です。自社メディアであるため、掲載するテーマや内容などすべてを自社の判断で決められます。
これは他のメディア手法と比較して大きな強みです。
たとえば、新聞や雑誌などの従来型メディアでは、掲載内容や表現方法に制限があり、編集部の意向に沿わなければなりません。SNSにおいても、プラットフォームのガイドラインや特性に合わせた発信が求められます。
オウンドメディアでは、顧客のニーズや市場の変化に応じて迅速にコンテンツを修正・更新することが可能です。たとえば、ある記事の反応が良ければ、関連コンテンツを追加したり、逆に反応が薄いテーマは見直したりすることができます。
また、自社の戦略変更に合わせて、コンテンツの方向性を柔軟に調整することも可能です。
コンテンツが資産になり長期的な効果を生む
もう一つの重要な特徴は、作成したコンテンツが企業の資産として長期的に効果を生み出し続ける点です。
一度公開したコンテンツは継続的にユーザーにアクセスされ、価値を提供し続けます。
特にSEO(検索エンジン最適化)を考慮したコンテンツ制作を行うことで、検索エンジンからの継続的な流入が期待できます。上位表示されるようになった記事は、数年にわたって安定した流入を生み出しますし、広告と違い、予算がなくなると効果が途切れることもありません。
オウンドメディアの6つのメリット

オウンドメディアを運用することのメリットは多岐にわたり、マーケティング活動の効率化だけではなく、ブランディングや採用、さらには社内の知識共有まで、様々な面で企業成長を支えます。
具体的にどのようなメリットがあるのか、一つずつご紹介します。
①ファンを作ることができる
オウンドメディアのメリットの一つは、企業のファンを作ることができる点です。
人は繰り返し接するものに対して好意を抱きやすくなります。オウンドメディアを通じて定期的に有益な情報に触れることで、読者は自然とその企業に対する信頼感を高めていきます。
たとえば、業界の最新トレンドや役立つノウハウを提供し続けることで「この企業は専門知識が豊富で信頼できる」という印象を形成できるのです。
特に専門性の高い業界では、オウンドメディアを通じた知識の共有が信頼獲得に直結し、商品やサービスの選択時に大きな影響を与えます。
また、オウンドメディアはブランディングの強力なツールでもあります。企業理念やビジョンに沿うコンテンツを発信することで、単なる商品やサービスの提供者ではなく、価値観を共有できるパートナーとして認識されるようになります。
②見込み顧客が増やせる
オウンドメディアの運用により、質の高い見込み顧客の獲得が可能になります。
SEO対策されたコンテンツは、特定のキーワードで検索しているユーザー、つまり既にその商品やサービスに関心を持っている潜在顧客にリーチできます。
オウンドメディアを通じて獲得した見込み顧客は、既に企業や商品サービスについて一定の知識を持っているため、問い合わせや商談の段階で基本的な情報提供に費やす時間を削減できるなど、営業プロセスの効率化にもつながります。
さらに、コンテンツへの反応を分析することで、どのような情報に関心を持っているかを把握し、より効果的なアプローチや顧客ニーズに合ったコミュニケーションを実現できます。
③中長期的に広告宣伝費が抑えられる
オウンドメディアへの投資は、中長期的に見ると広告宣伝費の削減につながります。
広告は出稿している期間のみ効果がありますが、オウンドメディアのコンテンツは一度作成すれば継続的な集客が可能です。
特にSEO効果が高まった記事は、数年にわたって検索エンジンから継続的な流入をもたらします。これは従来のリスティング広告などと比較すると、長期的なコストパフォーマンスが非常に高いのが特徴です。
また、オウンドメディアはSNSや広告と組み合わせることで、さらに効果を高めることができます。
オウンドメディアの良質なコンテンツをSNSで拡散したり、リスティング広告のランディングページとして活用したりすることで、各施策の効果を相乗的に高めることが可能です。
オウンドメディアは初期投資と継続的な運用が必要なものの、中長期的に見れば広告宣伝費の削減に大きく貢献する施策といえるでしょう。
④採用につながる
企業のオウンドメディアは、顧客獲得だけでなく、優秀な人材の採用にも大きく貢献します。
企業の価値観や社風、業務内容を伝えるコンテンツを通じて、求職者に対して深い企業理解を促すことができ、価値観を共有できる人材の獲得につながります。
特に社員インタビューや日常業務の紹介、専門知識を共有する記事は、その企業で働く魅力を具体的に伝えることができます。これにより企業と求職者のミスマッチを減らし、企業文化に合った人材の応募を増やす効果があります。
オウンドメディアで企業の専門性や先進性を示すことで、業界内での存在感を高め、「この会社で働きたい」と思わせる魅力も創出できるでしょう。
⑤社員研修に活用できる
オウンドメディアは、外部向けの情報発信だけでなく、社内の知識共有や社員教育にも効果的に活用できます。
たとえば、専門知識や業界情報、商品サービスの特徴などを体系的にまとめたコンテンツは、社員教育の貴重な教材となるでしょう。また、顧客からよく受ける質問とその回答をまとめた記事は、営業担当者の知識向上にも役立ちます。
さらに、オウンドメディアのコンテンツ作成プロセス自体が、社員の専門性向上につながります。記事を執筆するためには、テーマについて深く調査・分析し、わかりやすく体系化する必要があるため、担当社員の知識が整理され、深い理解が促進されます。
このように、オウンドメディアは外部への情報発信だけでなく、社内の知識管理・共有システムにおいても価値を持ち、組織全体の成長を促進する資産となるのです。
⑥PRリソースになる
オウンドメディアは、企業のPR活動を強化するための重要なリソースにもなります。
蓄積された質の高いコンテンツを様々な広報活動に転用することで、多様なチャネルで一貫性のある情報発信が可能になります。
以下は、PR活動への活用方法です。
・寄稿記事作成の効率化
既存コンテンツをベースにすることで、一から執筆するよりも効率的に質の高い寄稿記事を作成できます。
・メディア取材対応の向上
オウンドメディアで整理された情報により、取材時に一貫性のあるコメントを提供できます。
・書籍出版の素材として活用
連載記事などをまとめることで、業界書や解説書として出版することが可能です。これにより、企業の専門性を広い読者層にアピールできます。
・SNS投稿の素材として活用
記事のポイントをTwitterで発信したり、インフォグラフィックをInstagramに投稿したりすることで、より多くのユーザーにリーチできます。
・メールマガジンコンテンツの充実
新着記事の紹介や過去の人気記事のピックアップなど、読者の関心に合わせた情報提供が可能になり、顧客との継続的なコミュニケーションを強化できます。
このように、様々な形でコンテンツを再利用・展開することで、効率的かつ一貫性のあるPR活動が実現できます。
オウンドメディア運用のデメリット

オウンドメディアには多くのメリットがある一方で、運用にあたって認識しておくべき課題やデメリットも存在します。
効果的なオウンドメディア運用を実現するためには、これらの課題を正しく理解し、必要なリソースや期間、運営体制について現実的な計画を立てることが重要です。
ここでは、オウンドメディア運用の主な4つの課題と、その対応策について解説します。
①膨大なリソースが必要
オウンドメディアの運用には、継続的なリソース投入が必要です。特に人的リソース、時間、予算面での負担は軽視できません。
以下は、オウンドメディア運用に必要な主なリソースです。
・人 :編集者、ライター、SEO担当者、デザイナーなど
・時間:企画、執筆、編集、公開、分析、改善の各プロセス
・予算:コンテンツ制作費、システム構築・運用費、外部専門家への委託費など
・技術:CMS(コンテンツ管理システム)、分析ツールなど
質の高いコンテンツを継続的に生産するためには、専門知識を持つライターやエディター、SEOの専門家など、複数の人材が必要になります。
また、コンテンツ制作だけでなく、システム構築、デザインなどの専門スキルや、編集、公開、分析、改善といった一連の業務プロセスも必要になり、社内のリソースだけでは不足する場合もあるでしょう。
リソース負担を軽減するためには、外部パートナーと連携しながら効率的なワークフローを確立することが有効です。
関連記事:オウンドメディアの費用 立ち上げから運用までのかかる費用を解説
②成果が出るまでに時間がかかる
オウンドメディアは即効性のあるマーケティング手法ではなく、成果が現れるまでに一定の時間を要します。
新しいコンテンツは、検索エンジンに評価されるまでに時間を要することも多く、目に見える成果が出始めるまでには最低でも半年程度の継続的な運用が必要とされています。
また、初期段階ではコンテンツ数が少ないため、ユーザーの流入数も限られます。コンテンツが蓄積され、ドメインの評価が高まり、ユーザーから信頼を獲得するまで、粘り強い価値提供が必要です。
以下は、オウンドメディアの成果タイムラインの一例です。
1〜3ヶ月目:基盤構築期(戦略策定、初期コンテンツ作成、システム整備)
4〜6ヶ月目:成長初期(流入増加、一部コンテンツの検索上位表示)
7〜12ヶ月目:安定成長期(安定した流入、認知度向上、コンバージョン増加)
1年以降 :本格的な成果実現(ブランド構築、安定したコンバージョン獲得)
このような性質を理解し、短期的な成果に一喜一憂しないほか、経営層や関係者にも適切な期待値を設定してもらうことが重要です。
③運営の難易度が高い
オウンドメディアは、単に記事を書いて公開するだけでは、期待する効果を得ることは難しいのが現実です。効果的な運営には、以下のような様々な専門知識と経験が必要となります。
・SEOの専門知識
キーワード調査、競合分析、コンテンツ最適化、技術的SEOなどの知識と、常に変化するアルゴリズムへの対応力が必要です。
関連記事:SEOライティングの10つのコツと、作成前に気をつけなくてはいけないポイント
・ターゲットユーザーへの深い理解
ユーザーが求める情報、使用する検索語句、抱える課題など、ニーズや行動パターンを正確に把握することが効果的なコンテンツ制作につながります。
・効果的な導線設計
情報提供だけでなく、読者を次のアクションへ導くためのCTA(行動喚起)や関連コンテンツへの誘導など、戦略的な設計が求められます。
・コンテンツ分析と定期的なメンテナンス
ユーザーの反応や競合コンテンツの状況、検索エンジンのアルゴリズム変更に対応して、コンテンツを定期的に更新・改善する必要があります。
これらの専門知識や作業を社内だけで完結させるのは負担となるでしょう。効果的な運営のためには、外部の専門家の支援を受け、段階的に社内のスキルを向上させていくことが重要です。
④客観的な視点の不足
最後に、オウンドメディアを社内メンバーだけで運営することの最も大きな課題は、客観的な価値判断が難しいという点です。
社内では当たり前の知識や経験も、外部からみると非常に価値のある情報であることがあります。逆に、社内で重要視している情報が、外部のユーザーにとっては関心が低いこともあります。
この「価値の非対称性」を正確に把握するためには、外部の視点が不可欠です。
また、コンテンツの切り口を考える際も、社内の発想だけではマンネリ化やネタ切れに陥りやすくなります。
外部のクリエイティブディレクターやコンテンツストラテジストなどの専門家の視点を取り入れることで、より多様で魅力的なコンテンツ開発が可能になります。
オウンドメディアを活用するべき企業

オウンドメディアはあらゆる企業にとって有効な手段ですが、特に一部の業種や企業特性において、その効果が最大化される傾向があります。
ここでは、特にオウンドメディア運用が効果的な企業の特徴について解説します。
ブランディングを強化したい企業
オウンドメディアは、ブランディングを強化したい企業にとって非常に効果的なツールです。
特に、競合他社との差別化が難しい業界では、製品やサービスの機能面だけでなく、企業の哲学や価値観、専門知識などの「ソフト面」での差別化が重要になります。
同じような製品を提供している競合が多い場合は、製品の背景にある考え方や開発ストーリー、使い方の提案など、付加価値となる情報を提供しましょう。これにより、顧客の心に響くブランドイメージを構築し、競合他社との差別化を図ることができます。
また、新興企業や知名度が低い企業にとっては、オウンドメディアを通じて業界内での存在感を高め、認知度を向上させる効果も期待できます。
ブランディングの強化を目的とする場合、単なる商品情報ではなく、企業の価値観や世界観を体現したコンテンツ作りが重要です。
広告依存から脱却したい企業
多くの業界でCPA(顧客獲得単価)が上昇する中、広告費の高騰や効果の低下に悩んでいる企業にとって、オウンドメディアは広告依存からの脱却を図る有効な手段です。
リスティング広告やSNS広告などは即効性がある反面、広告費の上昇や競争激化により、投資対効果が低下する傾向があります。
一方、オウンドメディアは初期投資と継続的な運用コストがかかるものの、長期的には広告に依存せずに安定した流入を得られるようになります。
また、広告とオウンドメディアを組み合わせることで、より効果的なマーケティング戦略を構築することも可能です。広告で集客した顧客をオウンドメディアで育成し、ロイヤルカスタマーへと発展させるなど、それぞれの強みを活かした戦略が考えられます。
商材の理解が難しい企業
製品やサービスの特性が複雑で、専門的な知識や技術を必要とする商材を扱う企業では、顧客の理解を深めるためのコンテンツが重要となります。
例えば、IT分野のSaaS(Software as a Service)や技術的なB2Bサービスでは、製品の機能や利点を短時間で理解してもらうことが難しいケースが多くあります。
また、美容や教育、法律などのコンシューマーサービスでも、サービスの価値や効果を正しく伝えるためには、丁寧な説明と事例の提示が必要です。
オウンドメディアを通じて、基本的な知識から応用例まで段階的に情報を提供することで、顧客の理解度を高め、購買意欲を促進することができます。
商材の理解促進を目的とする場合、専門用語の解説や具体的な使用例、導入事例など、顧客の疑問点を解消するコンテンツ作りが重要です。
専門性・IRのアピールをしたい企業
高度な専門性を持つ企業や、IR(投資家向け広報)に力を入れたい企業にとって、オウンドメディアは自社の専門性や企業価値を効果的に伝えるプラットフォームとなります。
製造業や建設業、医療関連企業など、専門的な技術や知識を持つ企業では、その専門性を一般消費者や取引先に伝えることが難しい場合があります。
オウンドメディアを通じて、自社の技術や研究開発の成果、業界動向の分析など、専門性の高い情報を継続的に発信することで、業界における存在感を高めることができます。
また、投資家にも財務情報だけでなく、企業の将来性や成長戦略、社会的価値などを包括的に伝えることで、投資家の理解と信頼を深めることができます。
専門性やIRのアピールを目的とする場合、単なる宣伝や商品説明ではなく、業界の課題や動向、自社の取り組みについて深い洞察を提供するコンテンツ作りが重要です。
オウンドメディア運用の成功事例

オウンドメディア運用の可能性や効果を理解するには、実際の成功事例を知ることが有効です。
異なる業界における成功事例から、効果的な運用のポイントについて学ぶことができるでしょう。
関連記事:6つのオウンドメディア成功事例を深掘り
ベネッセコーポレーション
教育大手のベネッセコーポレーション(以下、ベネッセ)のオウンドメディア「ベネッセ教育情報 みつかる、明日のまなび。」は、子育てや教育に関する幅広い情報を提供し、多くの保護者から支持を得ています。
ベネッセのオウンドメディア成功の最大の要因は、保護者のニーズを深く理解したコンテンツ開発にあります。「子どもの成長に関する悩み」「学習方法の選び方」「進学に関する情報」など、子育て中の保護者が真に知りたい情報を、専門家の知見と実践的なアドバイスを交えて提供しています。
特に効果的だったのは、子どもの発達段階や学年に応じた情報の整理です。
幼児期、小学生、中学生、高校生など、子どもの成長に合わせて必要な情報は変化するため、保護者は子どもの成長とともに継続的にサイトを訪問するようになります。
また、単なる情報提供にとどまらず、ワークシートのダウンロードや会員限定コンテンツなど、具体的な課題解決につながるツールも提供することで、情報収集から実際のアクションへとユーザーを導く導線が構築されています。
ベネッセのオウンドメディアは、教育に関する情報提供を通じて保護者との信頼関係を築き、最終的に教材や通信教育などの商品購入へとつなげる優れた事例といえるでしょう。
関連記事:【事例紹介】ベネッセ 〜インタラクティブなブランドWebコンテンツを多数企画制作〜
日本能率協会
一般社団法人日本能率協会(以下、JMA)は「産業振興」と「人材育成」を目的とした活動を行う団体で、数々の展示会やセミナーを開催しています。
JMAはオウンドメディア活用前も日経新聞などへの広告を行っていましたが、実際の来場者・出展者へのリーチが不足していたため、SEO・SEMを用いたデジタルPRの必要性がありました。
日本能率協会のオウンドメディア成功の鍵は、専門的な情報提供と戦略的なSEO対策の両立にあります。
業界トレンドやイノベーション事例の継続的な発信と、ビッグキーワード「展示会」での検索上位表示を目指したSEO戦略を展開しました。特に効果的だったのは、JMAが主催する展示会と連動したコンテンツ展開です。
出展企業の技術解説や業界キーパーソンのインタビューを通じて、リアルイベントとオンラインコンテンツの相乗効果を生み出すと同時に、これらの記事が出展企業からの質の高い被リンク獲得にもつながりました。
また、業界カテゴリ別のページや専門ライターによる高品質なコンテンツは、Google評価基準に合致し、検索エンジンとユーザー双方から高評価を得ました。
JMAのオウンドメディアは、単なる情報発信の場ではなく、業界のエコシステムを強化し、リアルとオンラインの両面でビジネスマッチングを促進する戦略的プラットフォームとして機能した優れた事例です。
関連記事:【事例紹介】日本能率協会 〜展示会オウンドメディアのSEO、ビッグキーワードで2位獲得〜
まとめ:オウンドメディアは企業の持続的な資産になる

オウンドメディアは、企業のファン獲得から見込み顧客の増加、広告費削減、採用や社員教育の強化、PRリソース化まで、様々な効果が期待できる資産です。
しかし、リソースの確保や継続的な運用、成果が出るまでの期間など、運営にあたって多くの壁が存在します。客観的な視点を持ちながら、SEOやコンテンツ戦略、ユーザー心理などを考慮した質の高いコンテンツを継続的に生み出すことは、多くの企業にとって容易ではありません。
シェイプウィンは、戦略企画とメディアリレーションを得意とするPRマーケティング・コンサルティング会社として、単なるSEO記事ではなく、ストーリーテリングを活用した行動変容につながるコンテンツ制作をサポートしています。
オウンドメディア、SEO、PR、マーケティングを総合的に捉えた支援が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
https://www.shapewin.co.jp/ownedmedia