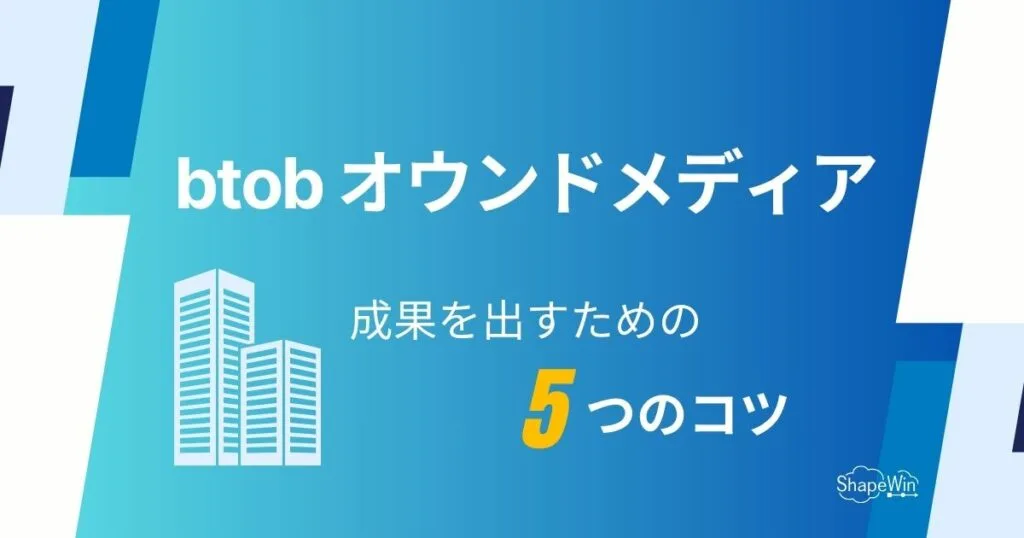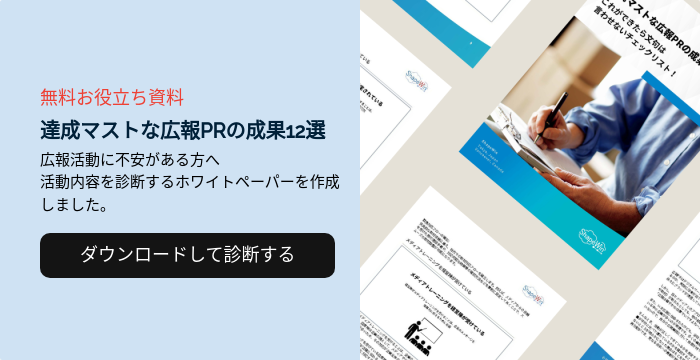BtoBマーケティングにおいて、オウンドメディアの活用はもはや選択肢ではなく前提になりつつあります。ただ、やみくもに記事を更新しても成果にはつながりません。
実際、MarkeZineの調査(※)では、オウンドメディアを運用している企業の6割が“人手不足”を課題に挙げており、3割以上が“効果実感までに1年以上かかった”と回答しています。
そこで本記事では、BtoB向けのオウンドメディアの役割や、検索意図に沿ったコンテンツ制作・KPI設計、そしてBtoBならではの運用ポイントを解説します。
(※)https://lany.co.jp/blog/btob-ownedmedia/
なぜBtoB企業にオウンドメディアが必要か

BtoB企業にとってオウンドメディアは、単なる情報発信の手段ではなく、マーケティング全体の成果を左右する重要な資産です。
従来の広告や営業チャネルだけではカバーしきれないリードの獲得や、顧客との関係構築において、オウンドメディアの果たす役割は年々大きくなっています。
はじめに、BtoB企業がオウンドメディアを導入・活用することで得られる具体的なメリットについて解説していきます。
リードの獲得チャネルになる
オウンドメディアは、BtoB企業にとって新たなリード獲得のチャネルとなります。
特に、広告費の高騰が続く中で、検索エンジンからのオーガニック流入を獲得できるメディアの価値は高まっています。自然検索で上位表示されることで、継続的かつ低コストで見込み顧客と接点を持つことが可能です。
広告のように費用をかけずとも、ユーザーが自発的に情報を探す”検索フェーズ”での接点を持てる点が、オウンドメディアの大きな強みです。
また、比較検討フェーズにいる顧客に向けた導線設計(例:記事→資料DL→問い合わせ)を施すことで、リードを育成しながら効率的に営業へとつなげることができます。
顧客のナーチャリング
BtoBの購買プロセスは長期にわたる傾向があり、一度の接点だけで成約に至るケースは稀です。オウンドメディアは、継続的な情報提供を通じて顧客との関係性を深める「ナーチャリング」において、非常に有効なツールとなります。
たとえば、FAQを記事化して定期的にメルマガで配信したり、ソーシャルメディアのコンテンツとして活用することで、顧客との接点を作ることにも繋がります。
また、ユーザーの行動履歴に応じたコンテンツ配信(例:特定ページを見たユーザーに関連情報を送る)を行うことで、よりパーソナライズされたナーチャリングが実現できます。
採用・広報にも有効な情報資産になる
オウンドメディアは、顧客との接点だけでなく、採用や広報活動においてもその効果を発揮します。特にBtoB企業にとって、企業のミッションやカルチャーをわかりやすく伝える場は貴重です。
たとえば、社員インタビューや社内の取り組みを紹介するコンテンツを発信することで、求職者に対して企業の魅力を伝えることができます。実際に、オウンドメディアを活用して採用エントリー数を伸ばした企業も多く見られます。
また、業界内でのプレゼンス向上にもつながり、広報的な役割を担うことも可能です。プレスリリースや外部講演などの情報をアーカイブすることで、企業の信頼性や専門性を高めることができます。
発信側が情報をコントロールできる
SNSや広告などの外部チャネルと異なり、オウンドメディアでは発信する情報をすべて自社でコントロールできます。これにより、伝えたいメッセージやトーンを一貫して維持することが可能となり、ブランディングの強化にもつながります。
また、外部サービスでは制限されがちなコンテンツの形式や文字数、表現方法なども自由に設計できるため、専門的かつ詳細な情報を掲載しやすくなります。たとえば、自社の強みや実績を事例記事として深掘りすることで、読み手に納得感を与えられます。
このように、自社の理念や価値観を正しく伝えるには、オウンドメディアのような自由度の高い発信プラットフォームが必要不可欠です。
コンテンツを転用できる
オウンドメディアで制作したコンテンツは、他のチャネルにも柔軟に転用可能です。
たとえば、記事をメルマガで再配信したり、営業資料やホワイトペーパーに再編集して活用することで、コンテンツのROI(費用対効果)を最大化できます。
さらに、商談時に記事URLを提示したり、SNSでのシェアによって新たな流入を得るなど、多様なシーンでの活用が期待できます。これにより、1つのコンテンツから複数のマーケティング成果を得ることができ、限られたリソースで効率的な運用が可能になります。
ブランドイメージの向上
オウンドメディアを通じて一貫性のある情報発信を行うことで、企業のブランドイメージ向上にも寄与します。特にBtoBでは、取引の信頼性や業界内での評価が購買判断に直結するため、情報発信のクオリティが重要な判断材料となります。
業界課題への見解や技術的知見、顧客事例の紹介などを通じて、企業の専門性や実績を伝えることで、信頼されるパートナーとしての地位を築くことができます。
結果として、商談時の説得力が高まったり、競合との差別化を図る材料にもなります。特に中小・スタートアップ企業においては、メディアを通じた印象形成がそのまま企業の印象へとつながるため、ブランディング戦略としてもオウンドメディアは非常に有効です。
BtoB向けのオウンドメディアコンテンツ戦略とは?

BtoB領域でオウンドメディアを成功させるには、ターゲットとの信頼関係を築きながら、自社の専門性と価値を正しく伝える必要があります。そのためには、コンテンツの切り口や導線設計に工夫が求められます。
ここでは、BtoBならではの効果的なコンテンツ戦略について具体的に解説します。
SEO集客の記事とストーリーテリングの記事を分ける
BtoBにおいては、SEOで検索上位を取ることは重要ですが、それだけではコンバージョン(CV)には直結しにくいのが実情です。なぜなら、BtoBの意思決定は複数のステークホルダーが関わるため、最終的な行動に至るまでに情報収集と検討のステップが長く複雑になるからです。
そのため、オウンドメディアでは「SEO集客用の記事」と「ブランド価値や思想を伝えるストーリーテリング記事」を明確に分けて設計する必要があります。SEO記事では検索意図に応える形で課題解決型のコンテンツを設け、そこからサービスページやホワイトペーパーにスムーズに誘導する導線を組み込みましょう。
一方で、ストーリーテリング記事は、企業の取り組みや理念、実際の顧客とのエピソードなどを通じて、読者の共感と信頼を醸成します。この「共感のストック」は、検討期間が長くなりがちなBtoBの顧客に対し、じわじわと影響を与える武器になります。
このように、SEOで流入を確保し、ストーリーテリングで信頼を構築し、サイト全体の導線でCVにつなげるという設計が、BtoBオウンドメディアに求められる基本構造です。
外部の人を巻き込んだコンテンツを作る
BtoB領域では、自社発信だけでは伝えられる情報に限界があります。特に、営業やマーケティング担当が執筆した記事は、どうしても「売るための視点」が強くなり、読者の信頼を得にくい傾向があります。
そこで重要になるのが、外部の視点を巻き込んだコンテンツづくりです。たとえば、実際の顧客企業の担当者にインタビューをしたり、業界の専門家からコメントをもらったりすることで、より客観性のある信頼性の高いコンテンツを作ることができます。
また、ソートリーダーシップ(業界を先導する立場)を発揮する記事として、企業の研究者や経営層の見解を掲載するのも効果的です。こうしたコンテンツは、単なる営業資料ではなく、読者が「読む価値がある」と感じるコンテンツへと昇華します。
オウンドメディアを信頼獲得のメディアとして機能させるには、外部の専門的な知見やリアルなユーザーの声を積極的に取り入れていくことが不可欠です。
営業資料からコンテンツを作成しない
よくあるオウンドメディアの失敗として、営業資料をそのまま記事に再構成してしまうケースがあります。しかし、これは効果的とは言えません。
なぜなら、営業資料は「すでに興味を持っている顧客」に向けて作られているため、検索してたどり着いた初見のユーザーには情報の前提が合わないからです。
そもそも、企業ホームページにあるサービス紹介ページと同じような情報を記事にしても、それ以上の価値を提供できず、SEO的にも評価されづらい傾向にあります。
本来、オウンドメディアの記事は「読者の課題解決」や「情報提供」に軸足を置くべきです。その上で、記事の中から自然にサービスページや資料請求ページへと導線を設けることが重要です。
つまり、ホームページとオウンドメディアの記事は目的が異なります。役割の違いを明確にして、適切な導線設計をすることで、サイト全体のパフォーマンスを引き上げることができます。
導入事例・Q&A・ホワイトペーパーを記事化する
BtoBでは、導入事例やQ&A、ホワイトペーパーといった情報が、見込み顧客の意思決定を後押しする重要なコンテンツになります。ただし、これらをただ全文公開するのではなく、「一部を記事化して部分的に見せる」する設計が効果的です。
たとえば、導入事例であれば、企業名や成果を簡潔に紹介し、詳しい内容はホワイトペーパーで解説するという形式が考えられます。これにより、読み手の興味を引きつつ、資料ダウンロードなどのアクションへとつなげる導線が生まれます。
また、Q&A記事も同様に、よくある質問を中心に設計しながら、「詳しい比較表はダウンロード資料へ」といった形でCVにつなげる動線が有効です。
こうした情報設計を行うことで、コンテンツは単なる読み物ではなく、マーケティング施策の一環として機能するようになります。つまり、コンテンツを「読ませて終わり」にせず、「行動につなげる」ための構成が、BtoBのオウンドメディアにおいては非常に重要なのです。
BtoBオウンドメディアを成功に導く6つのポイント

BtoB企業がオウンドメディアで成果を出すには、闇雲に記事を増やすのではなく、目的・設計・運用すべてを戦略的に組み立てる必要があります。
ここでは、特に意識すべき6つの成功要因について解説していきます。
①オウンドメディア運用の目的の明確化と、コンセプト設計
オウンドメディアの立ち上げ時点で最も重要なのが、「なぜ運用するのか」という目的を明確に定めることです。目的があいまいなまま進めてしまうと、記事のテーマがぶれ、社内からの理解や協力も得にくくなります。
たとえば、見込み顧客の獲得を重視するのか、ブランディングを目的とするのか、それとも採用活動や社内広報を視野に入れるのか。目的に応じて発信するべきコンテンツの切り口やトーン&マナーは大きく変わってきます。
また、運用目的に基づいて「誰に、何を、どのように届けるか」を言語化する「コンセプト設計」も欠かせません。これを設けておくことで、外部ライターとの連携時にも軸がぶれず、長期的な一貫性のある運営が可能になります。
②コンテンツの専門性と信頼性
BtoBオウンドメディアでは、情報の正確性や信頼性がとりわけ重視されます。BtoCと違い、購買決定プロセスが長く、複数人の意思決定が関わるため、表面的なトピックやトレンド記事では響きません。
そのため、単なるSEO対策ではなく、専門知識に裏付けられたコンテンツ設計が不可欠です。検索キーワードからユーザーのインサイトを読み解き、業界独自の視点や事例、数値データを加えることで独自性のある記事に仕上げましょう。
たとえば、「製造業 × ESG対応」「SaaS × 解約率改善」など、業界課題に即したテーマを扱うことで、信頼感を醸成しつつSEO効果も得られる構成になります。
③リード獲得を意識した設計(ホワイトペーパー・CTA)
BtoB企業のオウンドメディアは、最終的に「リード獲得」や「商談創出」につなげることが求められます。そのためには、記事からホワイトペーパーや無料相談、サービスページへと自然に遷移させる導線設計が必須です。
読者が求めている情報に対して、さらに深い資料を「CTA(コールトゥアクション)」で提示し、入力フォームでコンタクト情報を得る——この流れが王道の導線設計です。
たとえば、記事下部や本文内に以下のようなCTAを設置することで、効果的なリード獲得が可能になります。
• 「より詳しい事例をまとめた資料はこちら」
• 「無料テンプレートを今すぐダウンロード」
• 「このトピックについての無料相談を予約」
記事単体ではなく、サイト全体で「入り口(SEO記事)→本質的理解(ストーリー記事)→行動(CTA)」という流れを設計することが成功の鍵です。
④営業やカスタマーサクセスとの連携
オウンドメディア運営は、マーケティング部門だけで完結するものではありません。営業チームやカスタマーサクセス(CS)との連携がなければ、現場感覚を欠いた表面的な情報になりがちです。
特に以下の連携が重要です。
• 営業:よくある質問、反論されやすいポイント、顧客の決裁フロー
• CS:既存顧客が感じている課題、サポートに使えるFAQ記事
これらをコンテンツに反映させることで、購買前後のジャーニーを横断的にカバーするオウンドメディアが実現できます。
さらに、メールマガジンやSNS、展示会後のフォロー資料など、メディアのコンテンツを多チャネルに転用することで、運用効率を大幅に高めることも可能です。社内に点在するナレッジを拾い上げ、メディアを「組織全体の営業・広報ツール」として活用しましょう。
⑤自社ドメインで書かないと意味がない
「まずはNoteで試してみよう」という声もよく耳にします。たしかにNoteは手軽に始められ、初期SEOにも一定の効果が期待できますが、BtoBマーケティングという観点では不向きです。
最大の理由は、自社のドメインにコンテンツが蓄積されないことです。Noteは外部プラットフォームであるため、記事がいくらバズっても自社サイトの評価にはつながりません。また、仕様変更や広告表示のリスクもあり、ブランド表現の自由度も限定的です。
以下は、Noteと自社オウンドメディアの比較表です。
| 項目 | Note | オウンドメディア |
| 始めやすさ | ◎ | △(制作工数あり) |
| ドメインパワー | ○(Noteドメイン) | ○(自社次第) |
| ブランディング | △(デザイン制限あり) | ◎(自由に設計可能) |
| 収益化 | ◯(有料販売であれば可能) | ◎(広告・CV導線設計が可能) |
特に、BtoB企業でブランド力がまだ強くない場合、Note上で認知されるのは極めて困難です。むしろ「知らない人が何か言っているだけ」と認識され、逆効果になるリスクすらあります。
だからこそ、自社ドメインでオウンドメディアを構築し、サイト全体でブランドを育てていく姿勢が求められます。
⑥BtoBオウンドメディアのKPIを立てる
目的や体制が整ったら、次に必要なのが「KPI設計」です。KPI(重要業績評価指標)なしでは、どの施策が成果につながったのか判断がつかず、社内の理解や予算獲得も難しくなります。
特にBtoBの場合、成果が現れるまでに時間がかかるため、初期・中期・長期とフェーズを分けた指標設計が有効です。
以下はフェーズ別のKPI例です。
| フェーズ | 目的 | 主なKPI例 |
| 初期 | 認知拡大 | 記事数、PV数、滞在時間、SNS拡散数など |
| 中期 | リード獲得 | ホワイトペーパーDL数、CTAクリック率 |
| 長期 | 商談・受注 | 商談化率、CV数、受注件数 |
記事単体での成果だけを見るのではなく、オウンドメディア全体が「どれだけ売上につながったか」「顧客との関係性を深めたか」を可視化することが、長期運用の鍵になります。
オウンドメディアを始める前に準備すべきこと
オウンドメディアを成功に導くには、戦略やコンテンツの設計以前に、「組織として運用できるかどうか」という準備段階が非常に重要です。
ここでは、特に押さえておきたい2つのポイントについて解説します。
①運用体制とリソースの確保
オウンドメディアを継続して成長させるには、安定した運用体制と人的リソースの確保が不可欠です。しかし現実には、多くの企業が「担当者が1人しかいない」「兼務で時間が割けない」といった状況に悩まされています。
実際、Webマーケティングツール「ferret One」を提供する株式会社ベーシックの調査によれば、オウンドメディアを運用している企業の6割が“人手不足”を課題に挙げており、3割以上が“効果実感までに1年以上かかった”と回答しています。

また、よくある失敗例として、SEOを意識した記事をとにかく量産するものの、目的に合った設計やCV導線がないため、リード獲得に結びつかないケースが目立ちます。結果的に「記事は増えたけど、売上には貢献していない」と思い、運用をストップしてしまうことになります。
こうした事態を避けるには、以下のような役割分担と体制づくりが必要です。
・コンテンツ企画・編集責任者
・執筆者(社内or外部ライター)
・SEO/データ分析担当
・営業・カスタマーサクセスとの連携担当
これらが曖昧なまま始めてしまうと、更新が止まる・品質が下がるなど、信頼性を損なうリスクにもつながります。初期段階から社内外を含めた運用体制を設計しておくことが、メディアの持続的な成長を支える鍵となります。
②社内の理解と協力体制の構築
もう一つの重要な準備は、社内全体の理解と協力体制の醸成です。オウンドメディアは、マーケティング部門だけで完結するものではなく、営業、カスタマーサポート、開発、広報、経営層といった各部署との連携が求められます。

たとえば、営業現場から寄せられる顧客の声は、記事テーマのヒントになりますし、CSチームが抱える「よくある質問」はFAQコンテンツの素材になります。技術部門の知見は専門性の高いホワイトペーパーにも活かせます。
オウンドメディアの目的や全社的な価値を丁寧に共有し、関係者に自分ごと化してもらうことが重要です。初期段階で経営層を巻き込み、数値的なKPIや想定される成果を明確に示すことで、協力を得やすくなります。
BtoB企業のオウンドメディア成功事例

最後に、BtoB向けのオウンドメディア施策で成功している企業の事例を紹介します。
日本能率協会:専門的な情報提供と戦略的なSEO対策
一般社団法人日本能率協会(以下、JMA)は「産業振興」と「人材育成」を目的とした活動を行う団体で、数々の展示会やセミナーを開催しています。
JMAはオウンドメディア活用前も日経新聞などへの広告を行っていましたが、実際の来場者・出展者へのリーチが不足していたため、SEO・SEMを用いたデジタルPRの必要性がありました。
日本能率協会のオウンドメディア成功の鍵は、専門的な情報提供と戦略的なSEO対策の両立にあります。
業界トレンドやイノベーション事例の継続的な発信と、ビッグキーワード「展示会」での検索上位表示を目指したSEO戦略を展開しました。特に効果的だったのは、JMAが主催する展示会と連動したコンテンツ展開です。
出展企業の技術解説や業界キーパーソンのインタビューを通じて、リアルイベントとオンラインコンテンツの相乗効果を生み出すと同時に、これらの記事が出展企業からの質の高い被リンク獲得にもつながりました。
また、業界カテゴリ別のページや専門ライターによる高品質なコンテンツは、Google評価基準に合致し、検索エンジンとユーザー双方から高評価を得ました。
JMAのオウンドメディアは、単なる情報発信の場ではなく、業界のエコシステムを強化し、リアルとオンラインの両面でビジネスマッチングを促進する戦略的プラットフォームとして機能した優れた事例です。
関連記事:【日本能率協会】展示会オウンドメディアのSEO、ビッグキーワードで2位獲得
Hubspot:教育型コンテンツの提供
HubSpotは、インバウンドマーケティングという概念を世界的に広めたSaaS企業です。同社のオウンドメディア「HubSpotブログ」は、BtoBマーケティングに関する幅広いトピックを扱い、世界中の企業に影響を与えています。
このメディアの最大の特徴は、「教育型コンテンツ」に徹していることです。顧客の課題を先回りして解決するノウハウ記事、無料テンプレート、eBookなど、顧客にとって実用的な情報を惜しみなく公開しています。その結果、信頼性の高い情報源として認知され、オーガニック流入とリード獲得の両面で高い成果を上げています。
また、SEOを徹底的に意識したコンテンツ設計と、CTA(ホワイトペーパー、デモ依頼、無料ツールなど)を戦略的に配置することで、メディアからのCV導線も強化されています。検索ニーズに沿ったコンテンツ制作と、読者のステージに応じたCTA設計が、成果を出し続ける秘訣といえるでしょう。
HubSpotのように「顧客に教える姿勢」が一貫しているオウンドメディアは、長期的に見込み顧客の信頼を得るだけでなく、業界におけるソートリーダーシップの確立にもつながります。
川崎重工業株式会社:信頼性と技術力を発信
川崎重工業は、航空機、船舶、鉄道、エネルギー、ロボットなど幅広い産業機器を手がける重工メーカーです。BtoB企業としての信頼性と技術力を発信するため、オウンドメディアを活用しはじめました。
同社のオウンドメディアは、複雑で専門的な製品情報を、一般のビジネス層にも伝わるように「ストーリーテリング型コンテンツ」として再編集している点が特徴です。たとえば、「技術の背景にある開発ストーリー」や「社会課題を解決する技術の舞台裏」などをインタビュー形式で紹介し、企業としての思想や価値観を訴求しています。
さらに、SEOでは狙いにくい専門キーワードに関しても、既存顧客や業界関係者が求めるキーワードを中心に戦略を設計し、業界特化型の検索ニーズに応える構成となっています。
また、マーケティング部門だけでなく、エンジニアや広報部門との連携を密にし、コンテンツの品質と信頼性を両立。記事コンテンツはホワイトペーパーや営業資料にも活用され、社内外のナレッジとして資産化されています。
このように、川崎重工業のオウンドメディアは、専門性・信頼性・ストーリー性を兼ね備えたコンテンツ戦略によって、技術ブランドの強化とリードナーチャリングの両立を実現しています。
まとめ:設計の段階でのつまずきが後々まで影響する

BtoB企業にとって、オウンドメディアは単なる情報発信の手段ではなく、リード獲得・信頼構築・ブランディング・採用支援など多様な目的に対応できる「戦略的な資産」です。
とはいえ、オウンドメディアは「すぐに成果が出る施策」ではありません。リードの質を上げ、信頼を獲得し、長期的にCVへつなげるためには、SEOだけでなく、読者の行動変容を促す“ストーリーテリング”の視点が必要不可欠です。
オウンドメディアは成果が出るまでに時間がかかるからこそ、設計の段階でのつまずきが後々まで影響します。
シェイプウィンは、戦略企画とメディアリレーションを得意とするPRマーケティング・コンサルティング会社として、単なるSEO記事ではなく、ストーリーテリングを活用した行動変容につながるコンテンツ制作をサポートしています。
オウンドメディア、SEO、PR、マーケティングを総合的に捉えた支援が可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
https://www.shapewin.co.jp/ownedmedia