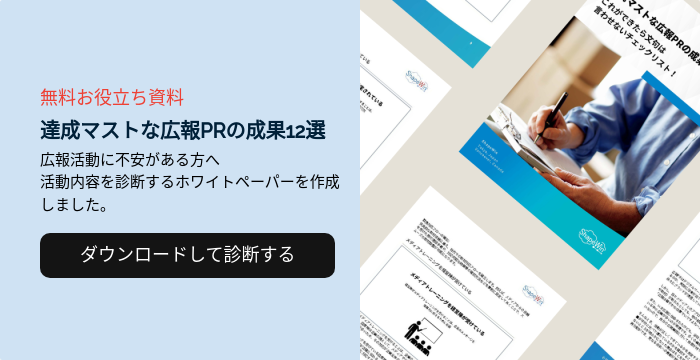採用競争が激化する現代において、優秀な人材を惹きつけるには「求人を出す」だけでは十分ではありません。
そこで注目されているのが「採用広報」。単なる情報発信ではなく、企業の魅力や文化を戦略的に伝えることで、求職者との接点を広げ、ミスマッチを防ぐ役割を担います。
本記事では、採用広報の意味からメリット、手法、成功事例、進め方、注意点までを網羅的に解説します。
採用広報とは?

「採用広報」とは、自社の魅力や価値観を社外に向けて積極的に発信し、求職者に「働きたい」と思ってもらうことに繋げる広報活動です。
求人情報や待遇面だけではなく、社員の働き方、社風、理念などを伝えることで企業理解を促し、応募や入社につなげます。
採用広報と似た言葉に「採用マーケティング」「採用ブランディング」がありますが、それぞれ意味が異なります。
まずはそれらの違いをみていきましょう。
採用マーケティング・採用ブランディングとの違い
| 定義 | ゴール | |
|---|---|---|
| 採用広報 | 企業の情報を発信し、認知拡大を目指す活動 | 企業の認知・理解向上 |
| 採用マーケティング | データやマーケティング手法を活用し、母集団形成や応募数増加を狙う活動 | 応募者数・質の向上 |
| 採用ブランディング | 企業価値や理念を発信し、「この会社で働きたい」と思ってもらうための活動 | 採用市場におけるポジション確立、入社意欲向上 |
採用広報が「外への情報発信」に軸足を置いているのに対し、採用マーケティングは「応募につなげる仕組みづくり」、採用ブランディングは「長期的な企業イメージの醸成」に重点があります。
つまり、採用広報は認知や関心を生み出す入口であり、その後の応募促進やブランド形成につながる土台といえます。
採用活動を成功させるには、広報・マーケティング・ブランディングを相互に連動させることが不可欠です。
採用ブランディングについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。
採用ブランディングとは?採用広報との違いや実践ポイントを解説
採用広報を行う部署・担当
中小企業では、人事部が採用広報を兼任していることも多いです。そこで、人事と広報の業務を完全に切り離すのではなく、PRやコーポレートコミュニケーションの観点を採用活動にも取り入れることで、より戦略的な発信が可能になります。
最近では「採用広報専任担当」を置く企業も増えており、社員インタビューやSNS発信を継続的に行う体制が整いつつあります。
採用広報が重要な理由
採用市場は情報過多の時代です。
求職者は求人媒体だけでなく、SNSや口コミサイト、社員の個人投稿など、あらゆるチャネルで企業を比較検討しています。
企業が積極的に情報発信しなければ、他社に埋もれてしまいます。さらに、情報不足によるミスマッチや早期離職を防ぐためにも、透明性の高い採用広報は欠かせません。
採用広報を行うメリット
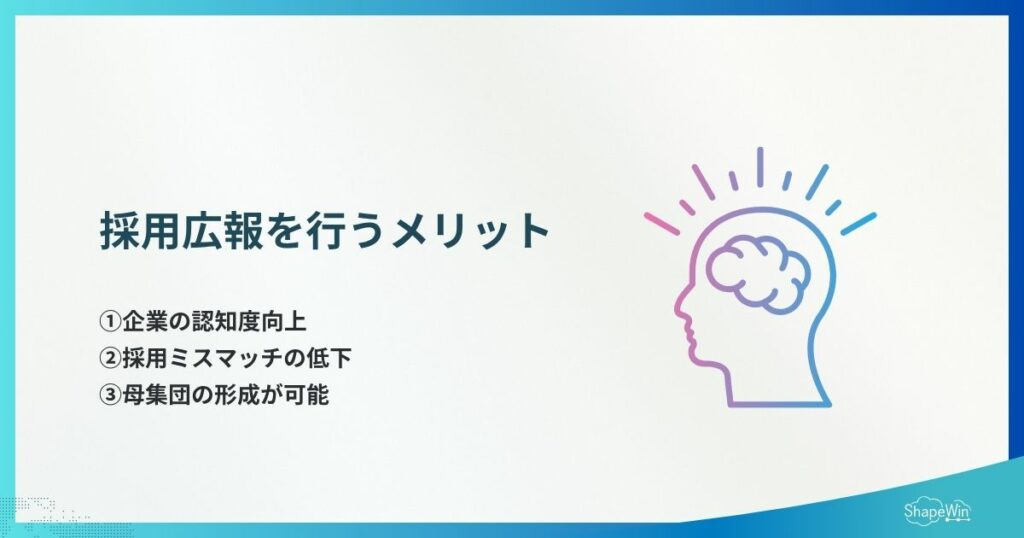
採用広報の導入によって得られるメリットは多岐にわたります。ここでは代表的な3点を解説します。
①企業の認知度向上
人材採用で最も大きな課題の一つは、そもそも「その会社の存在が知られていない」ことです。どれほど魅力的な制度や働き方があっても、認知されなければ応募につながりません。
そこで有効なのが、SNSやメディア露出を通じた情報発信です。特に若年層においては、「企業を知ったきっかけがSNSだった」というケースが年々増えており、早い段階からターゲット層にリーチするための重要な手段となっています。
②採用ミスマッチの低下
企業の価値観や働き方を発信することで、応募者は入社前に自分との相性を判断できます。
その結果、入社後のギャップによる早期退職を防ぎ、定着率向上につながります。
③母集団の形成が可能
採用広報は短期的な応募獲得だけでなく、中長期的な「候補者プール」の形成に役立ちます。普段から企業の魅力を発信しておくことで、潜在層にリーチし、採用のタイミングで自然に応募につなげられます。
採用広報の具体的な手法
採用広報は「求職者のカスタマージャーニー」を意識した多角的なアプローチが求められます。媒体ごとに特徴を理解し、目的に応じて組み合わせることが効果的です。
ここでは、具体的な手法を5つ紹介します。
SNS活用
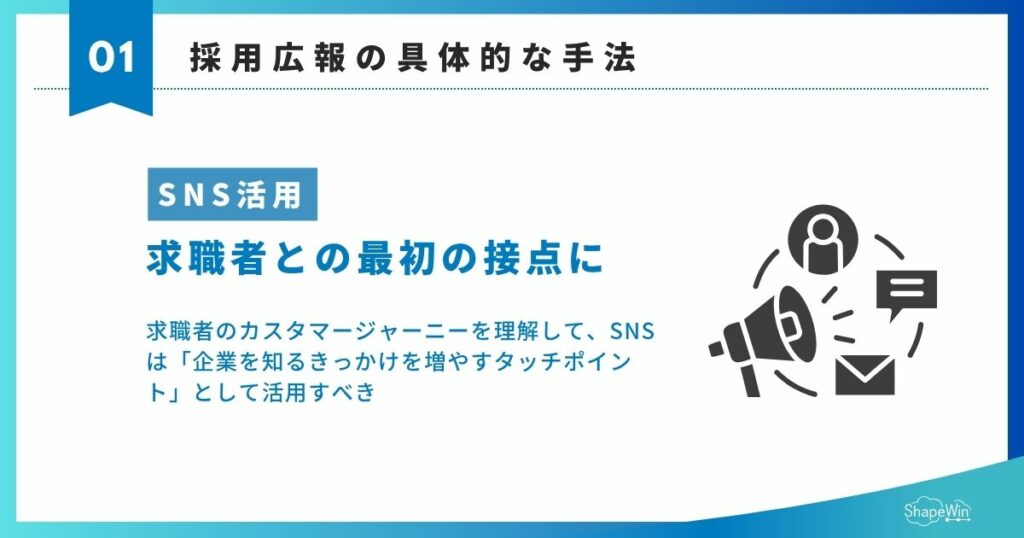
SNSは、求職者にとって最初の接点となる重要なチャネルです。
ただし「フォローし続けてもらうこと」は、なかなかハードルが高いとも言えます。そのため、求職者のカスタマージャーニーを理解して、SNSは「企業を知るきっかけを増やすタッチポイント」として活用すべきでしょう。特にX(旧Twitter)やInstagram、TikTokは、学生や若手層が自然に情報へ触れやすい媒体です。
なかでも注目されているのが「SNSを使ったライブ配信」です。
従来の企業説明会は、スーツ着用や形式的な質疑応答など堅苦しい雰囲気が強い一方、ライブ配信なら匿名で気軽に参加でき、学生にとって心理的ハードルが低いのが特徴です。
また、ライブ配信はチャット機能を使った双方向のやり取りが可能で、従来の説明会以上に学生の本音を引き出しやすいという強みもあります。
自然体のコミュニケーションが求められる現代において、SNS活用は好感度向上と企業理解の深化を同時に実現できる有効な手段と言えるでしょう。
SNS投稿の作り方に悩んでいる方はこちらの記事もご参照ください。
SNSコンテンツはこう作る!アイデア出しと作成の極意
オウンドメディア
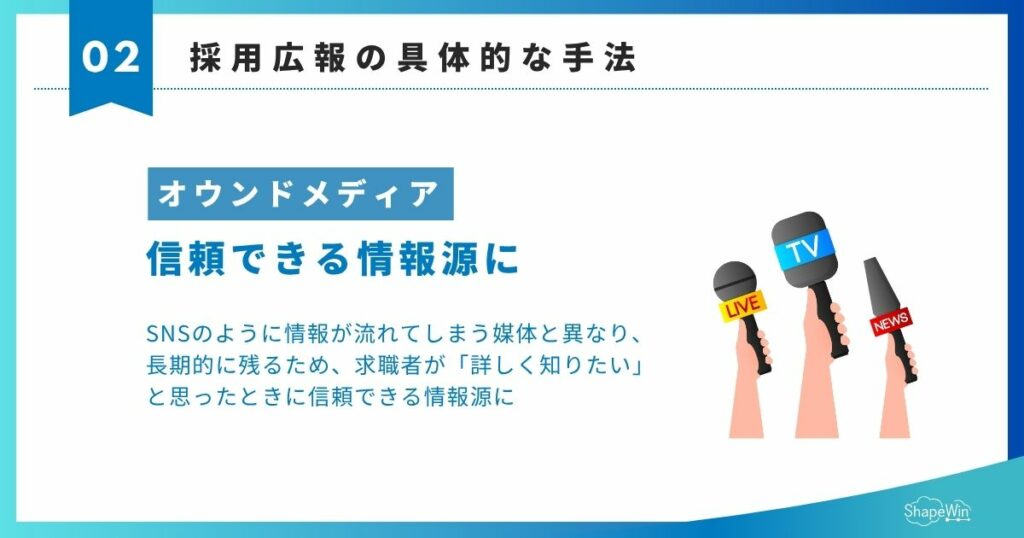
ブログや採用サイトといったオウンドメディアは、自社の理念や社員の声を「ストック型」で発信できるのが特徴です。
SNSのように情報が流れてしまう媒体と異なり、長期的に残るため、求職者が「詳しく知りたい」と思ったときに信頼できる情報源になります。
特に社員インタビューや日常の仕事紹介といった記事は、企業理解を深めるうえで効果的です。
オウンドメディアを持っていない方は、これを機に立ち上げを検討してみるのも良いかもしれません。
オウンドメディア立ち上げ完全ガイド 〜失敗しない体制構築と運用戦略〜
採用プラットフォーム
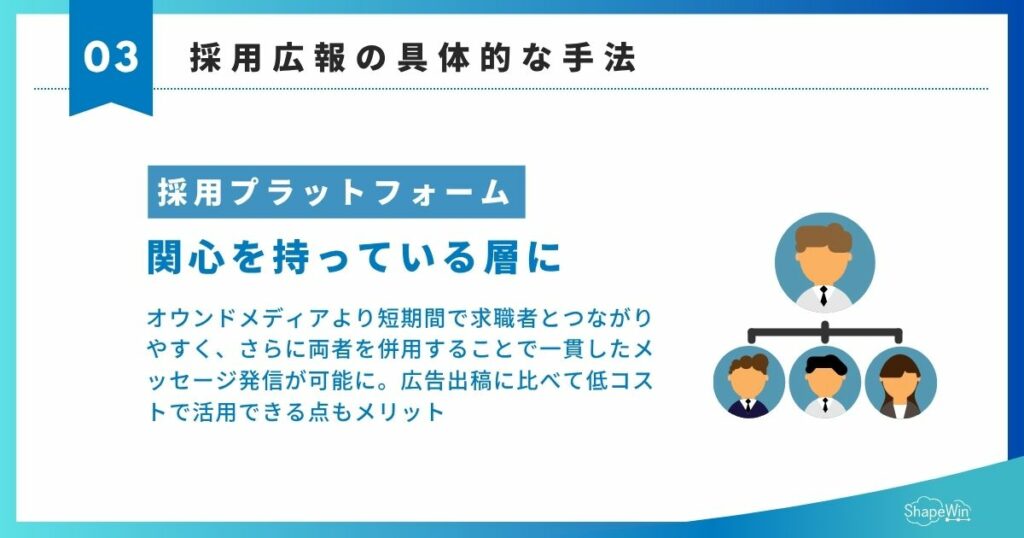
Wantedlyやnoteなどの外部サービスは、すでに就職・転職に関心を持っている層に直接アプローチできる点が強みです。
オウンドメディアより短期間で母集団形成につながりやすく、さらに両者を併用することで一貫したメッセージ発信が可能になります。広告出稿に比べ低コストで活用できる点もメリットです。
採用イベント
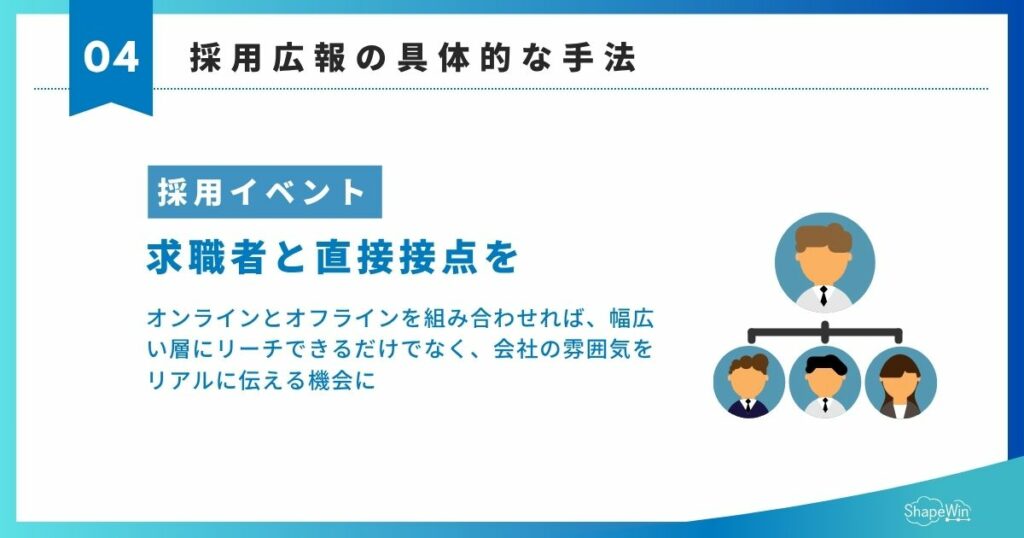
説明会やインターンシップ、キャリア系イベントは、求職者と直接接点を持てる場です。
オンラインとオフラインを組み合わせれば、幅広い層にリーチできるだけでなく、会社の雰囲気をリアルに伝える機会にもなります。
参加体験をその後に記事化してオウンドメディアで発信すれば、一次的なイベントを長期的な採用広報資産に変えることができます。
メディア掲載
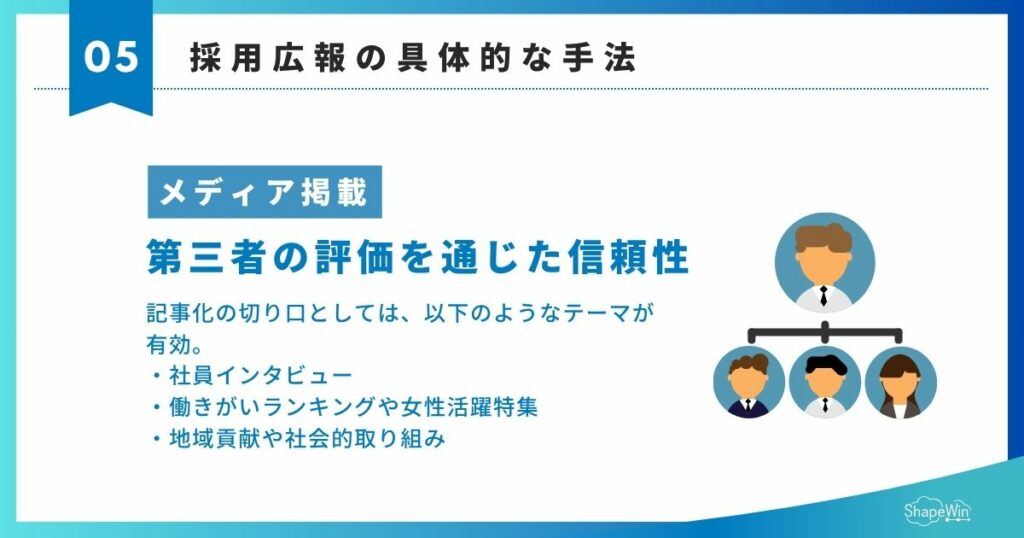
業界紙やキャリア系メディアに取り上げられることで、第三者の評価を通じた信頼性を獲得できます。記事化の切り口としては、以下のようなテーマが有効です。
・社員インタビュー
・働きがいランキングや女性活躍特集
・地域貢献や社会的取り組み
メディア露出は認知拡大だけでなく、企業ブランドの強化にも直結します。
メディア掲載を掴み取るためのメディアリレーションの方法については、これらの記事で解説しています。
採用広報の成功事例3選
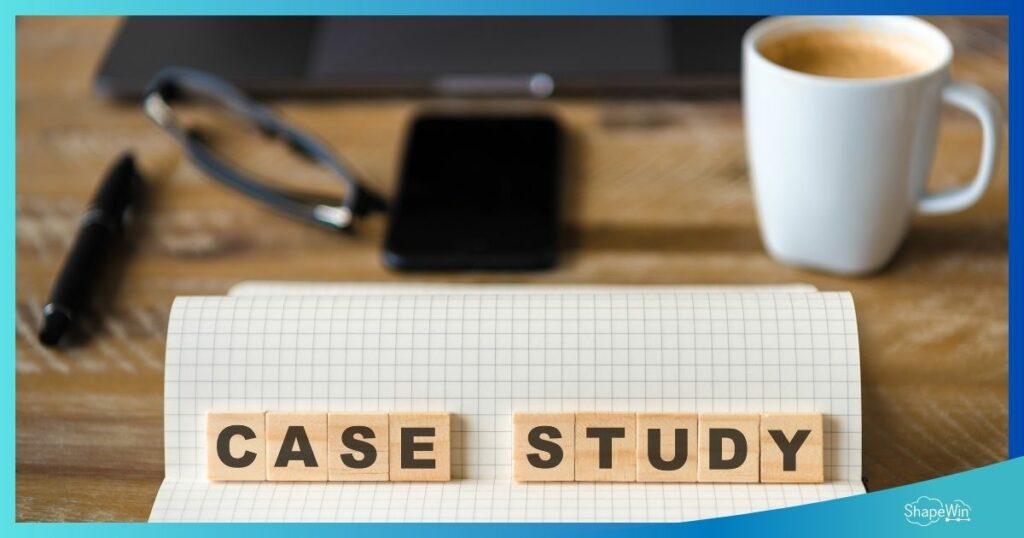
ここからは、実際に採用広報に成功した事例を紹介します。
採用広報の方法は、企業の規模や業界、ブランディングの方針によって適した形が変わります。他社の取り組みを参考にしながら、自社に活かせそうなポイントを探してみてください。
①社長自らが顔となりメッセージ発信:グローバルパートナーズ
グローバルパートナーズは、代表・山本康二氏が「社員の生き様をありのまま発信する」というスタンスを採用広報の中心に据えて成果をあげています。
社員の日常の仕事ぶりや昇給・降格といったリアルな社内ドラマ、さらには社長自身の経験や価値観までオープンに語ることで、他企業とは異なる透明性と共感性のあるブランドイメージを築いています。
公式サイト:https://www.global-p.com/recruit/
②TikTokで若者へのリーチに成功:三和交通
タクシー・ハイヤー事業を展開する三和交通は、若年層の採用増加を目的にTikTokを活用しています。ベテラン社員、通称「おじさん社員」がダンスや流行の音楽に合わせた動画に挑戦し、ユーモアと親しみやすさを前面に出したコンテンツが話題を呼びました。
実際に「TikTok2021上半期トレンド」のクリエイター部門にもノミネートされ、注目を集めています。
楽しさと誠実さを兼ね備えた発信が、企業理解と応募意欲の向上に直結した好事例と言えるでしょう。
三和交通@TAXI会社TikTokアカウント:https://www.tiktok.com/@sanwakotsu
③家族を巻き込んだ採用広報:主にメーカーや食品業界など
日本経済新聞の調査によると、新卒採用では学生本人だけでなく親の影響力も大きいとされています。
親は子どもの志望企業を調べたり、他の候補を薦めたりと意思決定に深く関与することが多く、内定後も企業の評判や信用性を気にするという結果が出ています。
そのため、採用広報に「親が安心できる情報」を戦略的に入れておくことも重要です。
たとえば、信頼できる媒体に広告を出稿して認知度を高めておく、会社説明会で保護者向けの説明を用意するなど、親世代の信頼を得ることで「親ブロック」を防ぐ効果が期待できます。
採用広報のステップ

採用広報は場当たり的に実施するのではなく、明確な戦略設計が必要です。
以下の5ステップを意識することで、施策を継続的に改善し、企業の資産として積み上げていくことができます。
①目的を設定する
まずは「何のために採用広報を行うのか」を明確にしましょう。目的によって施策の内容は大きく変わります。単に一つの施策を行うのではなく、これらの目的を理解しチャネルを横断的に連携させることが重要です。
・認知度を高めたい → SNSやメディア露出を重視
・応募者数を増やしたい → 採用プラットフォームの活用
・定着率を改善したい → 社員インタビューや働き方の発信
目的を曖昧にしたまま動き出すとリソースが分散し、効果が見えにくくなります。最初にゴールを設定することが成功の第一歩です。
②ペルソナを設定する
次に「誰に向けて発信するか」を明確にしましょう。性別や年齢、学歴といった基本属性だけでなく、「価値観」「仕事に求めるもの」「キャリア観」といった心理的な特徴も含めてペルソナを描きます。
たとえば「成長環境を求める理系学生」と「安定を重視する既卒層」では、響くメッセージや使うチャネルが全く異なります。ペルソナを具体的に設定することで、採用広報の方向性が定まり、結果としてコンテンツの精度も高まります。
関連記事:広報PRにおける「ペルソナ」とは?設定のポイントや成功例を解説
③コンテンツを作成する
採用広報の要は「何を発信するか」です。求職者にリアルな企業像を伝えることが重要になります。
・社員インタビュー(キャリアややりがいを語る)
・社内イベントや研修の紹介
・1日の仕事の流れを紹介するコンテンツ
ここで役立つのが「ジョハリの窓」のフレームワークです。
・企業が知っている強み × 外部も知っている強み → 発信すべき魅力
・企業が気づいていないが外部が評価している強み → 新しい発信テーマ
この整理を通じて、単なる会社紹介ではなく「共感を呼ぶストーリー」を作ることができます。
④媒体を選択して公開
作成したコンテンツをどこで発信するかは、目的とペルソナによって選び分ける必要があります。
SNS、オウンドメディア、採用プラットフォーム、メディア露出など複数の選択肢があるため、優先順位を決めることが重要です。
たとえば、若年層にはTikTokやInstagram、中堅層にはLinkedInや業界メディアといった具合にターゲットによって最適な媒体は異なります。
1つのチャネルに偏らず、複数のチャネルを組み合わせることで、接触機会を増やすことができます。
⑤効果検証を行い次に活かす
最後に欠かせないのが効果検証です。KPIを設定し、定量・定性的に改善サイクルを回しましょう。
・定量指標:PV数、応募数、エントリー率、内定承諾率
・定性指標:応募者アンケート、面接での志望理由、SNSでの反応
短期的な数値に一喜一憂せず、中長期で成果を測定することが大切です。改善を繰り返すことで、採用広報は資産として積み上がっていきます。
失敗しないための採用広報のポイント

採用広報は効果的に進めれば大きな成果につながりますが、やり方を誤ると期待した成果が得られないこともあります。ここでは、取り組む際に押さえておきたい注意点を解説します。
目的にあった施策・コンテンツを選ぶ
採用広報では、まず「何を達成したいのか」を明確にすることが欠かせません。認知度を高めたいのか、早期離職を防ぎたいのかによって取り組むべき施策は大きく変わります。
社員の協力を得る・巻き込む
現場で働く社員のリアルな声やストーリーは、採用広報において最も説得力のある情報です。
人事部だけで発信するのではなく、現場の社員が参加することで、より具体的で信頼性の高いコンテンツになります。また、社員参加型の企画は、社内の一体感を高める副次的効果もあります。
情報の一貫性を保つ
採用広報では、どの媒体や場面でも一貫した情報を伝えることが重要です。
求人票、SNS投稿、面接官の説明などがバラバラでは、応募者に不信感を与えてしまいます。そのため、発信内容の基準をあらかじめ定め、トーン&マナーを統一することで、メッセージの整合性を維持しましょう。
ポジティブな面のみを見せない
採用広報では、企業の魅力を発信することが目的ですが、ポジティブな面ばかりを強調するのは危険です。
最近では「ホワイトハラスメント(ホワハラ)」という言葉も広まっており、過剰に良い面だけをアピールすると、入社後に現実とのギャップが生じてしまいます。
その結果、不満や離職につながるリスクが高まります。
ありのままの情報を伝えることで応募数は減るかもしれませんが、その分「自社に合った人材」が集まり、長期的には定着率の向上につながります。
まとめ:接点の多さと共感の深さが重要

採用市場には情報があふれ、求職者はSNSや口コミサイトを通じて企業を多角的に調べる時代になりました。そのため、採用広報の役割は単なる情報発信にとどまらず、「信頼感」や「共感」を通じて応募意欲を高めることにあります。
社員インタビューやライブ配信、メディア掲載などを駆使すれば、求職者の企業理解を促進し、ミスマッチを防ぐことができるでしょう。
しかし、実際には多様なチャネルや手法が存在し、どこに力を入れるべきか判断するのは簡単ではありません。
シェイプウィンは、SNSからPR戦略、SEOまでを横断的に支援し、採用広報に直結する成果へと導きます。効果的なアプローチを模索している方は、まずはお気軽にご相談ください。