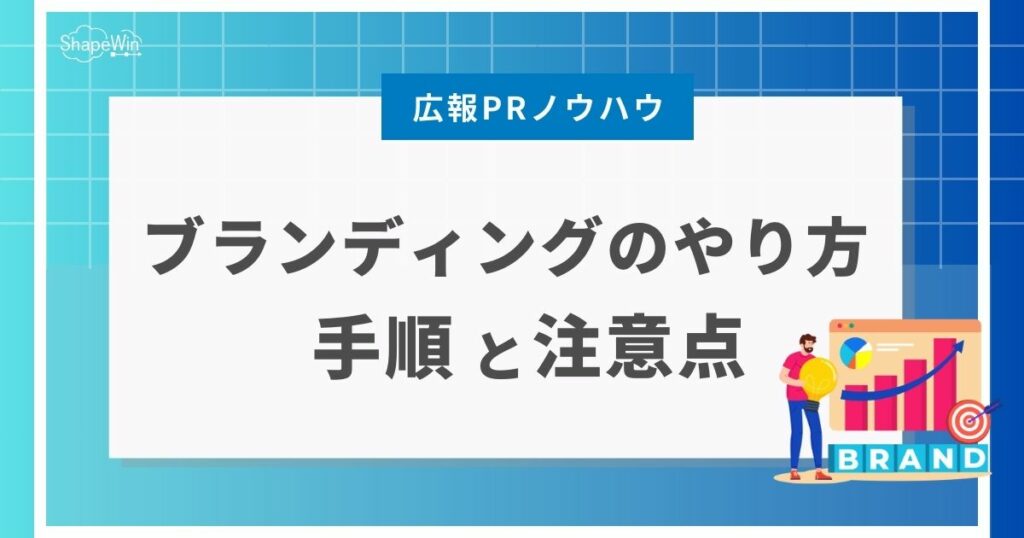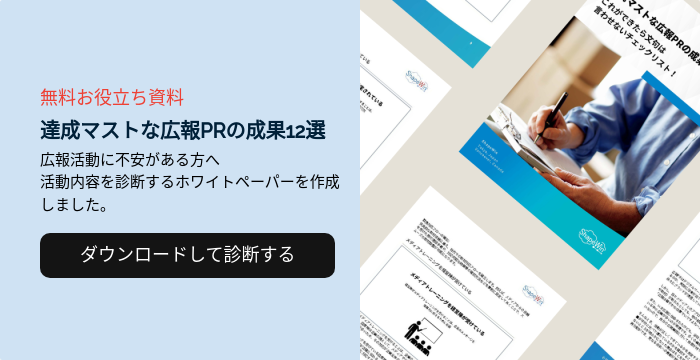自社の商品やサービスが、どの市場で、どのような顧客層に対して、どんな価値を持っているのか。業界内での自社の「位置」を明確にし、競合との差別化を図ることがブランディングです。
ブランディングを確立させるために、ブランディングの立て方や、ブランディングでやってはいけないことを知っておくことは非常に重要と言えます。
本記事では、企業が継続的にブランドを育てていくためのコツや考え方、活用しやすいフレームワークや方法までを、実践的に解説します。
ブランディングのメリットは?

マーケティングにおけるブランディングは、ほぼポジショニングと同じものと言っても過言ではありません。
自社の商品やサービスが、どの市場で、どのような顧客層に対して、どんな価値を持っているのか。その「位置」を明確にし、競合との差別化を図ることがブランディングの本質です。
重要なのは、自社が勝てる場所=ポジションを定め、その立ち位置を一貫して守り抜くことです。たとえば、「安さ」を前面に出すのも一つの戦略です。価格競争を避けたい場合は、「品質」や「デザイン性」「ストーリー性」など他の軸で勝負します。
関連記事:広報とブランディングの違いとは?それぞれの役割や目的、PR方法について解説
まずはじめに、ブランディングを行うことによる4つのメリットを解説します。
①顧客満足度の向上
ブランディングによって顧客が企業に対して持つ期待やイメージが明確になると、商品やサービスの提供体験に対する満足度も向上します。
これは、顧客が「想像通り」「期待通り」だと感じるからです。一貫性あるブランドは、信頼感を醸成し、リピーターを生み出します。
②価格競争からの脱却
競合と同じ土俵で比較されないようにするには、価格以外の価値を明確に打ち出す必要があります。ブランディングはそれを可能にする有効な手段です。
自社の世界観や専門性、ストーリーに共感してくれる顧客を獲得することで、価格ではなく「価値」で選ばれる存在になれるのです。
③広告費用を削減できる
ブランドが認知されていれば、少ない広告費でも顧客の信頼を得られます。
たとえば、口コミやSNSでの自然な拡散が生まれやすくなることで、広告依存から脱却できるでしょう。ブランド価値が高まれば、高額な広告に頼らなくても、指名検索やリピートで安定した集客が可能になるのです。
④採用強化につながる
ブランディングは、顧客だけでなく、求職者にも強く影響します。
明確な理念やビジョン、世界観を持つ企業には、その考えに共感する人材が集まります。
特に中小企業にとっては、採用力そのものが競争力に直結するため、ブランディングが採用活動にも直結することを忘れてはなりません。
ブランディングの基本5ステップ

ここでは、広報・マーケティング担当者向けに、商品・サービスのブランディングを進める上で欠かせない5つのステップをご紹介します。
①ブランドのターゲット層の決定
誰に向けてブランド(商品・サービス)を発信するのかを明確にすることが、ブランディングの出発点です。
性別、年齢、居住地、職業、ライフスタイルなどの定量的なデモグラフィック情報に加え、価値観やニーズといった定性的なペルソナ設計が重要です。
マーケ担当者や営業現場の声、既存顧客のデータも活用しましょう。
②自社の強みや競合のリサーチ
次に、自社と競合の比較を通じて「勝てるポジション」を見極めます。
SWOT分析(Strength, Weakness, Opportunity, Threat)や3C分析(Company, Customer, Competitor)を用い、自社の強みを明確にするとともに、競合が訴求していない価値を見つけましょう。
また、ユーザーインタビューやアンケートを通じた定量調査も重要です。
③ブランドの核となるコンセプトの定義
ターゲットと競合の状況を踏まえたうえで、ブランドの中核となるコンセプト・バリュー・ビジョンを定めます。
たとえば、「職人品質」「家族の安心」といったコンセプトです。
キーメッセージとして、一言で表現できる文言も用意しましょう。社内外のコミュニケーションにおける軸になります。
④一貫性ある表現の設計
ブランドの世界観を統一して表現するには、ロゴ、カラー、フォント、キャッチコピー、デザイン、トーン&マナーを整理し、ガイドラインにまとめます。
特に行っておくべき項目は「やってはいけないこと(DO/DON’T)」の設定です。ブランドイメージを崩さないために、表現のルールを明確にしておく必要があります。
⑤社内・外部発信と浸透
どれほど優れたブランド戦略でも、社員がブランドに共感しておらず、日々の業務で体現できていないと、社外からの信頼は得ることができません。
社内説明会や社内報、ワークショップなどを通じて、共通理解と共感を醸成しましょう。
また、プレスリリース、SNS、オウンドメディア、展示会など、それぞれのチャネルの役割を明確にし、戦略的に社外に向けても情報発信を行いましょう。
PR会社や制作パートナーとの連携も有効です。
関連記事:プレスリリースとは?一番初めに知っておきたい基本まとめ
参考になるブランディング構築事例

中小企業にとってブランディングは「資本力に頼らずに差別化できる」有力な武器です。
ここでは、実際のブランド構築の事例を3つ紹介します。それぞれの戦略の背景や成果から、自社に活かせるヒントを見つけてみてください。
チャットワーク:視覚情報による差別化は効果的
メッセージングアプリの「チャットワーク」は、色彩による差別化戦略で成果を上げた良い事例です。
多くの競合が青を基調としたUIを採用する中、チャットワークは赤系の色をアイデンティティカラーとして採用。これにより、視覚的な識別性と記憶への定着率を高めました。
視覚はブランディングにおいて最初に作用する要素です。色彩心理学の観点でも「赤」は行動を促す色であり、ビジネスチャットという即時性が求められるツールには適した選択といえます。
結果として、色から連想される機能性や使い勝手がブランド価値と結びつき、他社との差別化に成功しました。
X(旧Twitter):リブランディングには時間がかかる
2023年、Twitterは社名を「X」に変更し、大胆なリブランディングを図りました。
この変更は大きな話題を呼びましたが、今でも「Twitter」と呼び続けるユーザーも多く、完全な移行には時間がかかっています。
この事例は、ブランドの認知は一朝一夕に変えられるものではないという事実を示しています。
ユーザーの記憶に根づいたブランドは、名称やロゴを変更してもすぐに受け入れられるとは限りません。つまり、リブランディングを行う場合は、戦略的な計画と長期的な視点が必要不可欠なのです。
GAP:コアメッセージと一貫性が重要
アパレルブランドのGAPは、バナナリパブリック(高価格帯)とオールドネイビー(低価格帯)という姉妹ブランドを展開しましたが、GAP本体のポジショニングが曖昧になってしまいました。
中小企業にも言えることですが、ブランドは「何を選ぶか」よりも「何を選ばないか」が重要です。
複数のポジションを同時に取るとコアメッセージがぼやけ、顧客にとってわかりづらいブランドになるおそれがあります。明確な戦略と一貫性こそがブランドの信頼性を支えるのです。
ブランディングの手法
ブランディングはロゴやスローガンだけでなく、さまざまな手法によって強化・運用されます。
ここでは、代表的な6つの手法を紹介します。
動画コンテンツの作成

ブランドの世界観やストーリーをダイレクトに伝える手段として、動画コンテンツは非常に有効です。
特にSNSやYouTubeなどのチャネルでは、短尺動画やドキュメンタリー調のインタビュー動画が人気を集めています。
動画は「誰が、何のために、どんな想いで」商品・サービスを届けているのかを視覚と聴覚で訴求でき、エモーショナルな共感を得やすいのが特徴です。
ブランドブックの作成

企業の価値観や行動指針、コミュニケーションルールなどを明文化しておくことで、社内外で一貫性ある発信が実現できます。
特にPR活動においては、「出るべきでないメディア」「使ってはいけない言葉」など、NG項目を明確にしておくことも重要です。
オウンドメディア・SNSの活用

ブランディングにおいて、継続的にメッセージを届ける場としてオウンドメディアやSNSは欠かせません。
オウンドメディアは深い内容を語る場、SNSは即時的に共感を集める場として、それぞれ役割を分けて活用しましょう。
特にBtoB領域では、オウンドメディアがリード獲得やブランドストーリー共有の場として効果を発揮します。
インフルエンサー・アンバサダーの活用

自社のブランドに共感し、応援してくれるインフルエンサーを巻き込むことで、信頼性の高いブランド形成が可能になります。
注意すべきは「ブランドにふさわしい人を選ぶ」こと。高級ブランドが安易に無料配布を行うことでファンが離れてしまうことがあるように、ブランドと整合性が取れていないと、むしろ逆効果になることがあります。
関連記事:インスタグラムでインフルエンサーマーケティング|成功のポイントは?
店舗などの体験設計

リアルな接点での「体験」も、ブランディングにおいては重要な要素です。
たとえば、接客スタッフのトーンや立ち居振る舞い、店内BGM、香り、ディスプレイなど、五感に訴える要素はすべてブランド体験の一部です。
ブランドの世界観に即した体験を提供することで、記憶に残る印象を築けます。
ノベルティ・パッケージデザインの作成

ブランドロゴが入ったグッズや、ユニークなパッケージデザインも、ブランディングにおける重要な接点です。
ノベルティは日常使いされることで接触頻度を高め、無意識下でのブランド定着を促します。パッケージもまた、第一印象を左右する重要な要素であり、開封体験にまでこだわる企業も増えています。
まとめ:明確な戦略がブランディングの鍵を握る

ブランドとは、単なる見た目や言葉ではなく、「どう見られたいか」「なぜその価値を届けるのか」を社内外に明確に伝え続ける設計そのものです。
ブランディングに成功した企業は、ターゲット設定やブランドコンセプト、社内浸透、表現手法において一貫性を持っています。
ブランド構築は、単発の施策ではなく、事業戦略・社内体制・情報発信が連動して初めて機能します。しかし、日々の業務に追われる中で、すべてを自力で整えるのは決して簡単ではありません。
シェイプウィンでは、SNS運用からSEO対策、PR施策までを一貫させた、総合的なブランディグ支援が可能です。
無料相談も承っていますので、まずはお気軽にご相談ください。