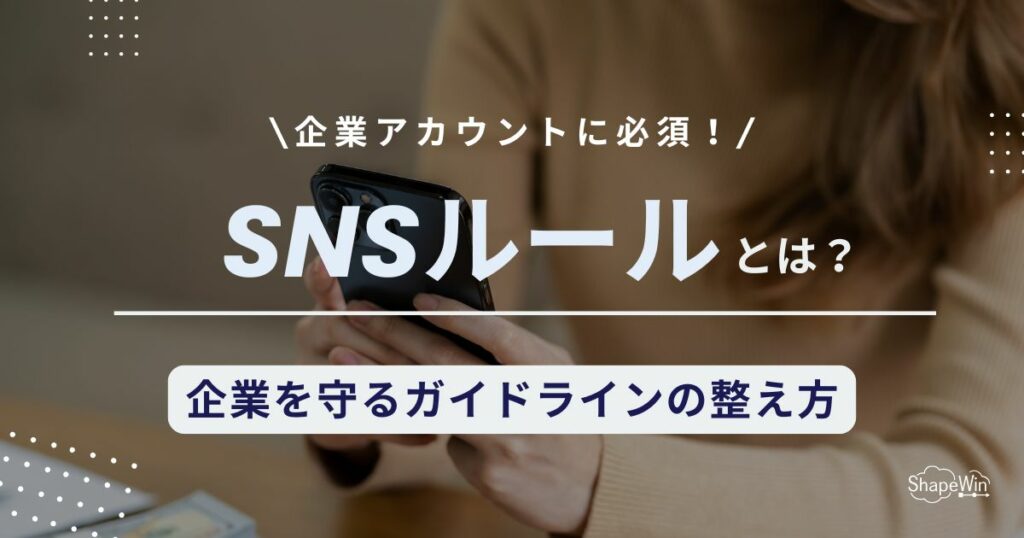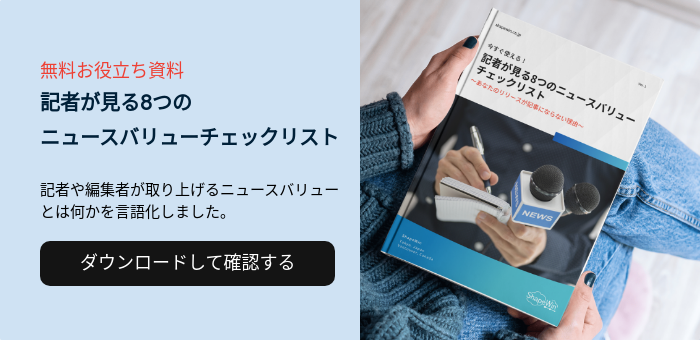SNSを活用した情報発信が当たり前となった今、「ルールの必要性は感じているけれど、何から手をつければいいのかわからない」「担当者によって投稿内容やクオリティにばらつきが出てしまう」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
社内SNSや公式アカウントの運用は、ちょっとした投稿が炎上や情報漏洩につながり、企業の信頼を一気に揺るがすリスクと常に隣り合わせです。また、属人化による運用トラブルや社外からの批判も珍しくありません。
本記事では、SNS運用ルールが必要な理由から、ガイドラインの種類、作成時の注意点、実際の炎上事例までを網羅的に解説します。信頼される企業コミュニケーションの基盤づくりに、ぜひお役立てください。
関連記事:企業SNS運用の成功法則!効果を最大化する戦略とは?
SNS運用ルールが必要な理由

SNSは企業にとって強力な情報発信ツールである一方、リスクも内包しています。
不適切な投稿や情報漏洩、誤情報の拡散などが発生すれば、企業の信頼は一瞬で失われかねません。
ここでは、なぜSNS運用ルールが必要なのか、その理由について解説します。
炎上や情報漏洩のリスクを最小化できる
企業がSNSを活用する上で最も懸念されるのが、炎上リスクです。
社員の不用意な投稿が思わぬ批判を招き、企業のブランドイメージを傷つけてしまうケースも少なくありません。さらに、社内情報の漏洩や誤解を招く投稿が、株価にまで影響することもあります。
こうした事態を防ぐためには、SNS利用に関するルールやポリシーを策定し、社員全体に周知徹底する必要があります。SNSガイドラインの整備は、リスク回避だけでなく、企業全体の情報発信の質を高める基盤となります。
投稿の属人化を防ぐことができる
SNS運用ルールを公式ガイドラインとして文書化することで、担当者ごとの投稿クオリティのばらつきを抑えることができます。
企業アカウントが担当者個人の裁量に依存してしまうと属人化が進み、担当者が交代した際に運用が混乱する可能性があります。
明文化された運用マニュアルがあれば、誰が担当しても投稿の品質と一貫性が保たれ、アカウント運用の継続性が担保されます。
企業価値や信頼を損なうリスクを回避できる
SNSの投稿は、企業イメージそのものに直結します。特に企業の看板を背負って情報発信するアカウントにおいては、投稿一つで企業価値が毀損するリスクもあるため、運用ポリシーの整備は不可欠です。
たとえば、差別的発言や事実誤認などが拡散されると、企業に対する信頼は大きく損なわれます。SNSポリシーを整備することで、企業としてのスタンスを明確にし、信頼性の高い運用が可能になります。
関連記事:失敗しないための危機管理広報マスターガイド!危機管理の基本から応用までを解説
SNS運用ルールの種類

SNS運用ルールと一口に言っても、目的や対象者によって複数の種類があります。それぞれの違いを把握することで、自社に必要なルール整備の方向性が見えてきます。
公式SNS運用ガイドライン・マニュアル
これは企業の公式アカウントを担当する従業員向けの運用マニュアルです。
投稿フロー、承認体制、投稿タイミング、緊急時の対応ルールなどをまとめます。
たとえば、「投稿前に必ずダブルチェックを行う」「炎上が発生した場合は○○部と連携して対応する」など、具体的な運用ルールを定めておくことで、トラブル時にも迅速な対応が可能になります。
ソーシャルメディアポリシー
こちらは企業として、ソーシャルメディア上でどのような姿勢を取るかを社外向けに示す文書です。
公式アカウントのスタンス、発信の目的、コメント対応方針、免責事項などを明記し、利用者と企業の関係性を記載します。
顧客や取引先に安心して企業のSNSを利用してもらうための信頼構築手段として有効です。
ソーシャルメディアガイドライン
従業員が私的にSNSを利用する際のルールをまとめたガイドラインです。
たとえ個人のアカウントであっても、企業名をプロフィールに記載していたり、所属が特定できるような投稿内容である場合、企業の評価に影響を与える可能性があります。
そのため、「企業秘密を漏洩しない」「社名を明記する際は事前に承認を得る」などのルールを明確にしておくことが重要です。
SNS運用ルールの作るポイント

SNSルールは、ただ作ればよいというものではありません。実効性のある運用ルールを策定するには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
目的を明確にする
まず、SNSルールを作成する目的を明確にしましょう。
「何のためにルールを作るのか」「誰が対象なのか」「どの範囲に適用するのか」といった基本設計を曖昧にすると、形骸化したガイドラインになってしまいます。
目的が「炎上リスクを防ぐため」であれば、それに対する具体的なルールや事例を盛り込みます。従業員の教育に活用するのであれば、社内研修資料としての利用も視野に入れて設計しましょう。
社内の関係部署と連携する
SNSルールの策定は、広報部門だけで完結させるべきではありません。
法務部門や総務部門、情報セキュリティ部門などと連携し、著作権、肖像権、情報漏洩、ハラスメント対策など、リスクの網羅性を担保しましょう。
特に、著作権や商標権などの知的財産に関するリテラシーを高めることは、炎上や訴訟リスクを回避するうえで重要です。
公開場所や認知方法を決める
ルールを作っても、対象者に認知されなければ意味がありません。社内ポータルサイトやイントラネットに掲載するだけでなく、定期的な周知・研修を通じて従業員の意識を高める取り組みが必要です。
また、社外向けのポリシーは企業サイトのフッターなど、誰もが閲覧しやすい場所に設置し、透明性を確保しましょう。
実際にあったトラブル事例

SNS運用に関するトラブルは非常に数多く存在します。
ここでは、実際に起きたトラブルと、それに対して講じた対応策を紹介し、SNSルール整備の重要性をより具体的にお伝えします。
不適切な投稿による炎上
ある企業では、しかし、海外市場を意識した投稿を日本でもそのまま使用したところ、海外では好評だったにもかかわらず、日本では批判的なコメントが相次ぎ、炎上につながってしまいました。
シェイプウィンではこの企業のガイドラインを日本市場向けに再設計し、投稿基準を文化的背景に合わせて調整したところ、ネガティブコメントがほぼゼロとなり、炎上リスクの大幅な低減に成功しました。
炎上が他のSNSにも波及
一つの炎上が他のSNSへと波及するケースは、近年ますます増加傾向にあります。
2019年、ディズニー映画『アナと雪の女王2』の公開に合わせて、7人の漫画家・クリエイターが作品の感想を漫画形式でSNSに投稿するというプロモーション企画が展開されました。
一連の投稿は、公開タイミングや共通のハッシュタグが見られたことから、ネット上では「ステルスマーケティングではないか」という疑念が早くから浮上していました。
やがて、これらの投稿が有償で依頼された広告にもかかわらず、広告表示がなされていなかったことが明らかとなります。その後、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社は、「PR表記の必要性について、関係者間での確認が不十分だった」として、公式に謝罪を発表する事態となりました。
こうしたトラブルを防ぐためにも、インフルエンサーや企業は投稿時のルールや広告表示のガイドラインを正しく理解し、法的な確認を怠らないことが今後ますます求められています。さらに、危機発生時の社内対応フローの確立も、企業価値を守るうえで重要な施策となります。
インフルエンサーとのトラブル
インフルエンサーとのコラボ企画では、双方のスケジュールや段取りに依存するため、思わぬトラブルが発生しやすい傾向があります。
たとえば、施策当日の進行に不備があり、予定していたイベントが実施されなかったという事例もあります。このようなトラブルは、主催側とインフルエンサー側双方にとって信頼を失うことにつながりかねません。
このようなケースでは、事前に「予備日の設定」「トラブル時の対応ルール」「責任の所在を明確にした契約書」の整備が不可欠です。
まとめ:SNSガイドラインの策定が企業を守る

SNSルールの整備を怠ったことによって企業が信頼を失い、深刻な損失を被る事例は後を絶ちません。たった一つの投稿が原因で炎上が拡大し、株価の下落、顧客離れ、従業員の士気低下にまで波及するリスクがあります。
こうしたリスクを未然に防ぐには、ルールの整備にとどまらず、組織としての継続的な体制構築と運用が不可欠です。
シェイプウィンでは、SNS運用の戦略設計から日々の投稿管理、危機対応マニュアルの作成、社内ガイドラインの構築、さらには炎上リスクに備えた研修まで、企業のSNS活用をトータルで支援しています。
広報・人事・マーケティング部門が安心して運用できるよう、業種や組織の特性に応じたカスタマイズも可能です。
無料相談も承っていますので、SNS活用に不安を感じている方や、ガイドラインを形だけで終わらせたくないという担当者の方は、ぜひ一度ご相談ください。