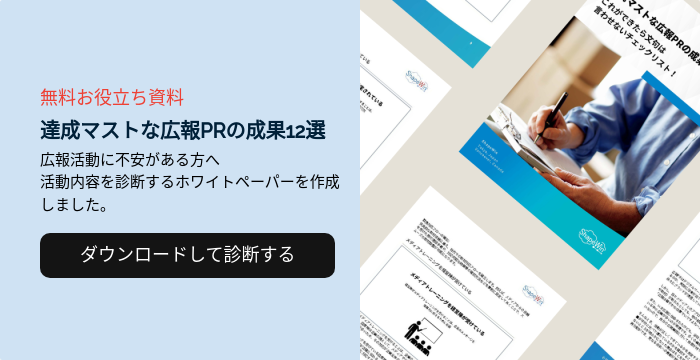インフルエンサーマーケティングは、多くの企業が注目する施策です。
認知拡大やECの売上アップなど多くのメリットが語られる一方で、実施直前に「本当にリスクはないのか?」「炎上やトラブルの可能性は?」と不安になる担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、インフルエンサーマーケティングの主なデメリットとその回避方法、実際に起きた失敗事例までを詳しく解説します。
インフルエンサーマーケティングのリスクに注意すべき理由

インフルエンサーマーケティングの活用が急速に進む中で、リスクに対する関心も高まっています。
まずは、なぜリスクを押さえておくべきなのか見ていきましょう。
企業の信頼を損ねないため
SNS上では情報が一瞬で拡散されるため、インフルエンサーマーケティングの投稿ひとつが企業ブランドに大きな影響を与えることがあります。たとえ小さなミスでも、文脈を誤った表現や誤解を招く投稿が批判の対象となり、信頼の失墜につながる可能性は十分にあります。
企業としては「どのような形で伝えるか」「どんな価値観と結びつくか」を精査し、安易にバズを狙うのではなく、ブランドの一貫性を保った慎重な設計が求められます。
思わぬ炎上やコンプライアンス違反を起こす可能性があるため
魅力的なインフルエンサー施策に目を奪われがちですが、法令違反や社会的な炎上リスクを軽視することはできません。
特に広告表現や景品表示法、薬機法などの規制を把握しないまま投稿すると、重大な問題に発展する可能性があります。
また、投稿された内容が不適切と捉えられた場合、企業への批判が広がるリスクもあります。メリットだけに注目せず、リスクを想定した施策設計が、長期的に信頼を築く鍵となります。
インフルエンサーマーケティングの主なデメリット

ここでは、実際にインフルエンサーマーケティングを運用する中で企業が直面しやすい、5つのデメリットを解説します。
①ステルスマーケティングと思われやすい
インフルエンサーによる投稿があまりにも自然すぎると、広告であることが分かりづらく、消費者からステルスマーケティングと受け取られるリスクがあります。
特に「PR」「広告」などの明記がない場合、信頼を損なうだけでなく、景品表示法違反などの法的問題にも発展する可能性があります。
こういった事態を避けるためには、インフルエンサーとの事前調整と投稿ガイドラインの共有が欠かせません。
②インフルエンサー自身が炎上するリスクがある
過去の不適切発言やスキャンダルが原因で、起用したインフルエンサーが炎上するケースは少なくありません。
炎上はX(旧Twitter)からInstagram、YouTubeへと波及する可能性もあり、企業イメージの毀損につながります。投稿内容だけでなく、インフルエンサーの人となりや過去の投稿履歴までしっかりチェックする必要があります。
③インフルエンサー選定に失敗する
フォロワー数だけでインフルエンサーを選んでしまうと、ターゲットとのミスマッチが起こりやすく、思ったような効果が得られないことがあります。
特にEC商材やBtoCサービスは、購買につながる層とマッチしているかの見極めが重要です。また、選定には時間がかかり、キャスティングの難易度も高いため、効率的なプロセス設計が求められます。
④インフルエンサーのマネジメントが難しい
インフルエンサーは基本的に個人の裁量で動いているため、投稿のスケジュール管理や内容の事前確認がしづらい場合があります。また、細かい指定を嫌う傾向もあるため、企業側の意図が伝わらずに齟齬が生まれることも少なくありません。
トラブルを未然に防ぐためには、事前に信頼関係を築き、ガイドラインや報酬、対応ルールを明文化しておくことが重要です。
⑤定量的な費用対効果が分かりづらい
インフルエンサーマーケティングは、効果測定が難しいことも課題のひとつです。
売上やコンバージョンといった直接的な成果に結びつかないケースも多く、上層部への報告資料に苦慮することもあります。特に中長期でのブランドリフトや認知度向上を目的とする場合は、定量化の指標設計が不可欠です。
インフルエンサーマーケティングのリスクを回避する方法

ここでは、上記で紹介したデメリットを事前に回避・軽減するための具体的な対策を紹介します。リスクをゼロにすることは難しいものの、準備と設計次第で大幅に軽減できます。
契約書・ガイドラインの整備
インフルエンサーとのトラブルを防ぐためには、投稿内容のルールやスケジュール、報酬などを明文化した契約書の整備が欠かせません。
また、コンプライアンス遵守やブランド毀損を防ぐため、投稿ガイドラインを作成して共有することで、相互の認識を合わせることができます。
炎上対策マニュアルの策定
炎上が発生した際に慌てないためにも、社内での対応フローやメディア対応、投稿削除の判断基準などを事前に定めた炎上対策マニュアルを準備しておくことも必須です。
初動対応のスピードと誠実さが、ブランドを守る鍵になります。
関連記事:失敗しないための危機管理広報マスターガイド!危機管理の基本から応用までを解説
効果測定指標の設計
施策の費用対効果を明確にするためには、KPIを定義し、効果測定の仕組みを整える必要があります。
具体的には、クーポンコードの使用率、専用URLのクリック率、SNSからの流入CV数などが有効な指標になります。
投稿単位での効果が数値化できれば、次回以降の施策改善にも役立ちます。
信頼できるインフルエンサー会社に依頼する
インフルエンサーの選定やマネジメントに不安がある場合は、専門のインフルエンサーマーケティング会社に依頼するのも有効です。
経験豊富な代理店であれば、施策の設計から運用、レポーティングまでワンストップで対応してくれるため、企業担当者の負担を大きく軽減できます。
インフルエンサーマーケティングの失敗事例

インフルエンサーマーケティングには失敗例も存在します。ここでは実際のエピソードをもとに、対策の重要性を再確認しましょう。
ターゲットに合わない投稿による炎上
汎用的なマニュアルを使い回すことで、意図せぬリスクが発生するケースは少なくありません。
過去の成功事例をそのまま踏襲したり、業界や地域に合わない表現を流用したりすることで、誤解や炎上を招くリスクがあります。
実際に、欧米市場では好まれた表現をアジア圏でそのまま翻訳して投稿した結果、現地の価値観にそぐわず、批判が集まったケースもあります。
マニュアルやガイドラインは重要な土台ではあるものの、施策ごとにアップデートが必要です。市場環境やターゲットの感性、SNSのトレンドなどを踏まえてカスタマイズを行うことで、不要なトラブルを未然に防ぐことができます。
インフルエンサーとのトラブル
インフルエンサーとのトラブルでよく見られるのが、投稿内容やスケジュールに対する双方の認識齟齬です。
たとえば、投稿タイミングや表現方法に関する詳細が詰めきれておらず、企業側の期待と異なる内容が発信された結果、トラブルに発展するケースがあります。また、報酬や契約条件に関しての合意が曖昧な場合、投稿の有無や成果をめぐる争いが起こることもあります。
こうした事態を防ぐためには、投稿スケジュール、内容確認のフロー、万が一のトラブル時の対応方針を事前に明確化し、契約書に盛り込んでおくことが重要です。インフルエンサーとの信頼関係を維持するには、事前の調整と透明性のある取り決めを徹底しましょう。
事実と異なる発言による炎上
ある著名インフルエンサーが特定の美容商品のPR投稿を行った際に、成分表示が実際と異なるという指摘から炎上に発展した事例があります。
Xでの拡散がInstagram、YouTubeへと波及し、企業のブランドイメージを大きく損なう結果となりました。
炎上は一つのSNSに留まらず、複数のチャネルに広がるため、投稿前のチェック体制とリスク管理が不可欠です。
インフルエンサーマーケティングを成功に導くポイント

インフルエンサーマーケティングは、準備と設計次第で高い効果を得られる一方、成功には相応の労力とノウハウが求められます。
ここでは施策を成功させるための実践的なポイントを紹介します。
施策の目的を決める
まず最初に行うべきは、「なぜこの施策を実施するのか?」という目的の明確化です。
認知度向上、販売促進、サイト流入、ブランディングなど、目的によって最適なインフルエンサーやSNS、投稿内容が異なるためです。
目的が曖昧なまま施策を進めると、評価指標も不明確になり、結果として効果を実感しづらくなります。
商材に合ったプラットフォームとインフルエンサーを見極める
インフルエンサーと自社商品の世界観がマッチしていなければ、フォロワーからの共感は得られません。
商材やターゲット層ごとに、適切なプラットフォームと発信者を選ぶことが重要です。
たとえば、以下のような組み合わせが考えられます。
・美容・ファッション・健康食品などのToC商材 → Instagram
・ガジェット・教育・美容系の専門情報 → YouTube
・金融・アニメ・コンビニ食品など話題性重視 → X(旧Twitter)
インフルエンサーの世界観と自社のブランディングが一致していることで、自然な投稿となり、フォロワーからの信頼や反応にも良い影響を与えることが期待できます。
広告の規制・規則を守る
景品表示法や薬機法、プラットフォームごとの規約など、広告表現にはさまざまなルールがあります。
違反が発覚した場合、広告停止や炎上に発展するリスクがあります。投稿前には、文言や表現を法務部門や専門家と確認し、問題がないかを精査しましょう。
費用対効果を高めるため外注を利用する
施策のPDCAを効率的に回すためには、すべてを内製化しようとせず、外部パートナーの活用も有効な選択肢です。
インフルエンサー施策には、企画立案・キャスティング・投稿内容のディレクション・投稿後のモニタリングやレポーティングなど、多くの業務が発生します。
特にリソースが限られている企業では、これらすべてを自社でまかなおうとすると、時間的・人的負担が大きくなり、結果として施策の質が低下してしまうリスクがあります。
そのため、経験豊富なインフルエンサー専門会社に依頼することで、ターゲットに合ったキャスティングからトラブル対応、KPIに基づく分析までを一括で任せることが可能になります。
業務負荷の軽減だけでなく、専門知識に基づいた高精度な設計と運用が期待でき、施策の費用対効果も向上します。
まとめ:リスクを理解し、安全で効果的なインフルエンサー活用を

インフルエンサーマーケティングは、認知拡大やブランドイメージの向上を狙える魅力的な施策ですが、効果の見える化や再現性の確保といった課題も避けて通れません。
さらに、ステルスマーケティングと受け取られるリスクや、インフルエンサーの炎上、費用対効果の不透明さなど、さまざまなデメリットやリスクが存在します。
そのため、インフルエンサーマーケティングは単体で完結させるのではなく、SNS、SEO、PRなどの全体戦略の中に位置づけることが重要です。
シェイプウィンでは、SNS・SEO・PRなどの全体設計を通じて、インフルエンサーマーケティングの効果を最大限発揮するサポートを行っています。企画設計からキャスティング、投稿内容の監修、効果測定までを一貫して支援できる体制を整えており、目的に応じた最適な提案が可能です。
無料相談も承っていますので、まずはお気軽にご相談ください。