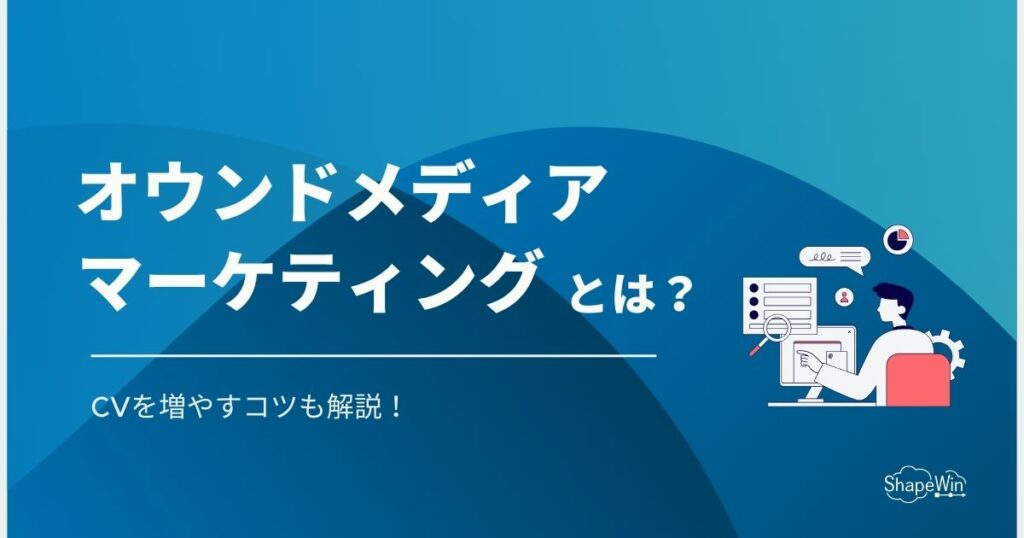検索広告のクリック率低下や広告費の高騰により、今、多くの企業が“次の一手”としてオウンドメディアに注目しています。しかし、ただ記事を更新するだけではマーケティング成果にはつながりません。
オウンドメディアの運用には、目的の明確化や戦略設計、KPI管理が欠かせないからです。
本記事では、「マーケティングにおけるオウンドメディアとは何か?」という基本から、運用方法、活用事例、コンテンツマーケティングやNoteとの違いまで、集客力のあるメディアを構築するために知っておきたい実践知をわかりやすく整理します。
オウンドメディアとは?

企業やブランドが自ら運営し、自由に情報発信できるオウンドメディアは、マーケティングにおける重要な土台です。SNSや広告と違い、発信の自由度や蓄積効果が高いため、中長期的な資産形成に適しています。
まずはじめに、オウンドメディアの基本的な特徴と他メディアとの違いを解説します。
コンテンツが資産になる
オウンドメディアの最大の特徴は、「コンテンツが資産になる」ことです。一度制作した記事やインタビュー、事例紹介などのコンテンツは、時間が経っても検索やSNSを通じて継続的に顧客を呼び込みます。
広告と異なり、出稿をやめても情報が残るため、長期的に成果を積み重ねていけるのが大きなメリットです。特に、SEOで上位表示された記事は月日を経ても安定した集客力を持ちます。実際、過去に制作した記事が半年後に問い合わせのきっかけになることも珍しくありません。
「育てるメディア」として、計画的に更新と改善を重ねることで、コンテンツは資産として企業価値を高めてくれる存在になります。
発信内容をコントロールできる
オウンドメディアでは、発信する情報やタイミング、表現方法まですべて自社でコントロールできます。これは、広告やSNSといった他チャネルにはない大きな強みです。
たとえば、SNSではアルゴリズムの変化によってリーチ数が上下しますが、オウンドメディアでは検索流入に加えて、メールマガジンや社内報など、幅広い導線を設計できます。また、掲載NGワードなどの外部制限もないため、自社の思想やストーリーを深く語ることができます。
ブランドの世界観を正しく伝えたい、複雑なサービス内容を丁寧に解説したいといった場合、発信の自由度が高いオウンドメディアが最適な場となります。
コンテンツマーケティングとオウンドメディアの違い
混同されがちですが、コンテンツマーケティングとオウンドメディアは明確に異なる概念です。簡単に言えば、コンテンツマーケティングは「施策」、オウンドメディアは「媒体」にあたります。
コンテンツマーケティングは、顧客の購買プロセスに合わせて有益な情報を提供し、信頼を獲得して行動へと導く手法です。その手段として活用されるのが、オウンドメディアというメディアになります。
たとえば、コンテンツマーケティングの一環としてホワイトペーパーを作成し、それを配信する場としてオウンドメディアを活用する。このように両者は密接に関係していますが、役割は異なります。マーケティング戦略全体の中で、オウンドメディアをどう活用するかが鍵となります。
noteとオウンドメディアの違い
近年では、個人や企業がNoteを使って情報発信するケースも増えています。Noteは手軽に始められるので、Noteを検討する方もいるかもしれません。
一方で、ブランディングやリード獲得といったマーケティング観点から見ると、特に知名度のないスタートアップや小規模事業者には、Note上で有名になることは難しいです。理由は以下の通りです。
| 項目 | Note | オウンドメディア |
| 始めやすさ | ◎ | △(制作工数あり) |
| ドメインパワー | ○(Note全体) | ○(自社次第) 被リンク施策で対策可能 |
| 記事のデザイン性 | △(デザイン制限あり) | ◎(自由に設計可能) |
| 収益化 | ◯(有料販売であれば可能) | ◎(広告・CV導線設計が可能) |
Noteはあくまで外部サービスであるため、プラットフォームの仕様変更や広告表示など、自社の意図しない制限も受ける可能性があります。企業として独自のブランドを築きたい場合は、自由度の高い自社ドメイン配下で発信するオウンドメディアの方が、中長期的な資産形成につながります。
オウンドメディアをマーケティングに活用する方法

オウンドメディアは、単なる情報発信の場ではなく、顧客との長期的な関係構築を支えるマーケティングの核です。
特にAISAS(認知→興味→検索→行動→共有)の流れに沿ってコンテンツを設計すれば、ユーザーの行動を促し、成果に繋がるメディアへと成長させることができます。
ここでは、各フェーズごとの活用方法を詳しく解説します。
ブランディング(A=Attention、I=Interest)
オウンドメディアは、企業の世界観や価値観を継続的かつ一貫して発信できる貴重な場です。ブランディングではまず、ユーザーに認知(Attention)してもらい、興味(Interest)を持たせる必要があります。
このフェーズでは、以下の要素が重要です。
• メディア全体のトーン&マナーを統一する
• 専門性のあるテーマに絞って継続発信する
• 検索意図に沿った記事でSEO上位を狙う
ジャンルを絞り、長期的にコンテンツを蓄積していくことで、検索エンジンでの評価も高まり、業界内でのポジショニング強化にもつながります。たとえば「BtoB SaaS」分野で一貫した情報発信をすることで、「この分野ならこの会社」と思われる信頼構築が可能です。
リード獲得(S=Search、A=Action)
次のフェーズでは、検索(Search)を通じて比較検討中の顧客にリーチし、アクション(Action)へとつなげます。広告費が高騰する中で、オウンドメディアは低コストかつ高効率でリード獲得が可能な手段として注目されています。
企業はこれまで、検索結果の上位に表示される「リスティング広告」や、Webサイトの広告枠に表示される「ディスプレイ広告」に依存してきました。しかしながら、実際のユーザー行動を見ると、自然検索の方がはるかに高いクリック率を誇っていることが明らかになっています。
たとえば、2017年にInternet Marketing Ninjasが発表した調査では、検索結果1位の自然検索リンクは21.12%のクリック率だったのに対し、リスティング広告は10.11%にとどまっています。また、2012年の別調査では、自然検索は広告の約4倍クリックされているにもかかわらず、投下されている広告費は約10分の1という結果も出ています。
| 順位 | 自然検索(※1) | リスティング広告(※2) |
| 1位 | 21.12% | 10.11% |
| 2位 | 10.65% | 7.28% |
| 3位 | 7.57% | 5.66% |
| 4位 | 4.66% | 4.04% |
| 5位 | 3.42% | 3.13% |
参照:https://www.sedesign.co.jp/marketing-blog
このような背景から、企業はクリック率の低いリスティング広告の比重を下げ、より信頼性が高く成果につながりやすい「自然検索」への投資を強化しています。オウンドメディアの制作は、まさにこの動きに合致するものといえるでしょう。
ポイントは以下のとおりです。
• 検索ニーズに対応したSEO記事の作成
• CTA(資料DL、問い合わせ、セミナー予約など)の明確な設置
• 比較フェーズ向けの導線設計(記事→ホワイトペーパーなど)
ユーザーは広告よりも信頼できる情報を求めて検索します。その際に、「自社の課題に刺さる」記事と出会えると、問い合わせや資料ダウンロードといった具体的な行動に移りやすくなります。
顧客のナーチャリング(I=Interest、A=Action)
オウンドメディアは、獲得したリードとの関係性を深めるナーチャリング(育成)の場としても有効です。メルマガや営業資料に流用できる「再利用性の高いコンテンツ」を揃えておくことで、顧客との接点を複数持つことができます。
活用例:
• メルマガで定期的にオウンドメディア記事を紹介
• 営業資料に記事URLや図表を活用
• セミナー後のフォロー資料として使い回す
顧客は一度で成約に至るとは限らないため、「信頼の積み上げ」が重要です。ナーチャリングに適したオウンドメディアを構築しておくことで、顧客の温度感に合わせたアプローチがしやすくなります。
カスタマーサポート(S=Share)
購入後のフェーズでは、顧客の満足度向上やロイヤルティ醸成を目的としたサポートコンテンツが有効です。FAQや活用事例、レシピ、ハウツー記事など、ユーザー自身が自社商品をうまく使いこなせるようにナビゲートします。
例:
• IT業界 → システムの設定マニュアル記事
• 食品業界 → 商品を使ったレシピ紹介
• SaaS → よくある質問やトラブル解決手順
満足した顧客がSNSや口コミでシェア(Share)することで、新たな集客へとつながる好循環が生まれます。
直接的な収益化
オウンドメディアはブランディングやリード獲得だけでなく、メディア自体を収益化することも可能です。代表的な手法には以下のようなものがあります。
• アフィリエイト収益(外部リンクで紹介料を得る)
• 広告掲載(バナーや記事広告)
• 有料コンテンツ販売(セミナー動画、ホワイトペーパー)
収益化を目指す場合は、コンテンツの質とターゲット層の精度が成功の鍵になります。「読まれる」「信頼される」メディアに育てることで、広告主やパートナー企業からの価値も高まり、マネタイズの選択肢が広がります。
オウンドメディアをマーケティングに活かすための4つのポイント

オウンドメディアを成果につなげるには、ただ記事を更新するだけでは不十分です。
目的やKPI、戦略、運用体制といった「土台」が曖昧なままだと、継続しても効果を実感できず、社内のモチベーション低下にもつながりかねません。
ここでは、オウンドメディアをマーケティング活動として機能させるために、最低限押さえておきたい4つのチェックポイントを解説します。
①目的の明確化
オウンドメディアを活用する第一歩は、何を目的にするのかをはっきりさせることです。たとえば「ブランディング」なのか「リード獲得」なのか、それとも「商品理解の促進」なのか、目的によってコンテンツの設計や集客チャネルは大きく変わります。
目的があいまいなままスタートしてしまうと、成果の判断基準が持てず、途中で方向性を見失うことも少なくありません。特にマーケティングでは、短期で結果が出にくいため、チーム内で共通の目標意識を持つことが欠かせません。
自社の課題と向き合い、「このメディアを通じて何を達成したいのか?」を言語化しておくことで、その後の戦略や評価の軸がブレずに進みます。
②KPIの設定
目的を定めたら、次はその達成度を測る指標(KPI)を設けることが重要です。KPIを決めていないと、「頑張って更新しているのに成果が見えない」といった曖昧な評価になりがちです。
KPIはフェーズごとに切り分けるとより効果的です。
| フェーズ | 目的 | KPI例 |
| 初期(立ち上げ) | 認知拡大 | PV数、SNSシェア数、流入キーワード数 |
| 中期(育成) | 関係構築・比較検討 | 滞在時間、回遊率、スクロール率 |
| 後期(成果) | CV獲得 | 資料DL数、問い合わせ数、成約数 |
目的に合ったKPIを設計しておくことで、データに基づいた改善がしやすくなり、PDCAも回しやすくなります。
どうしてる?オウンドメディアのKPIを徹底解説
③戦略が設計されているか
オウンドメディアの運用で見落としがちなのが、「誰に、どのタイミングで、どんな内容を届けるか」の設計です。これが戦略設計であり、単なるコンテンツ制作とは明確に区別する必要があります。
戦略設計には以下が含まれます。
• ターゲット設定(ペルソナの明確化)
• カスタマージャーニーの把握
• コンテンツの役割分担(集客/比較検討/CV後など)
• 検索ニーズやSNSトレンドの分析
• 外部チャネルとの連携(SNS、メルマガ、広告など)
このように、戦略があるかどうかで、同じ労力でも成果に大きな差が生まれます。「毎週ブログを書く」ことが目的化してしまう前に、「何のためにこの記事を出すのか」を必ず設計しましょう。
④運用体制が整っているか
どれだけ良い戦略を立てても、それを実行するための運用体制が不十分であれば成果は出ません。実際、オウンドメディア運用が頓挫する企業の多くは、社内の人手不足や役割不明確が原因です。
理想的な運用体制は、以下のような役割分担が整理されていることが重要です。
• コンテンツ企画:マーケ担当 or 編集責任者
• 執筆:社内ライター or 外注ライター
• 校正・編集:編集担当
• 効果測定・改善:分析担当 or マーケ責任者
また、全体の進行管理や品質管理が曖昧だと、更新が止まったりクオリティが下がったりするリスクがあります。外部の専門パートナーと連携して「部分的に外注」する体制を構築するのも、有効な選択肢のひとつです。
オウンドメディアの費用 立ち上げから運用までのかかる費用を解説
まとめ:目的・KPI・戦略・体制が重要

オウンドメディアマーケティングは、中長期で成果を積み重ねていく“資産型”の施策です。
だからこそ、目的・KPI・戦略・体制の4点が不十分なままでは、どれだけ時間をかけても思ったような成果にはつながりません。とくにリード獲得やナーチャリング、ブランディングなど、目的によって運用方法が異なるため、最初に設計を間違えると後戻りが難しくなります。
検索ユーザーが求めている「成果につながる運用のやり方」は、単発ではなくフェーズごとの設計があってこそ。オウンドメディアは重要な施策である反面、それだけではマーケティング全体を支えるには不十分です。
シェイプウィンは、日本ではまだ少ない「PR会社によるオウンドメディア支援」を行っているチームです。単なるSEO代行ではなく、行動変容を促すストーリー設計と広報・マーケティングの連携によって、御社の価値を社会に届ける支援を行います。まずはご相談からお気軽にご連絡ください。