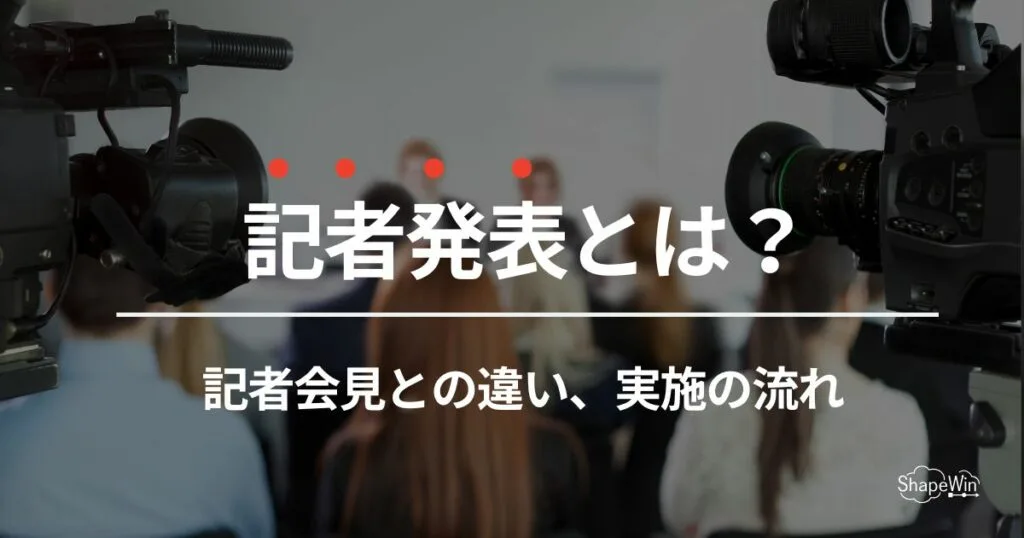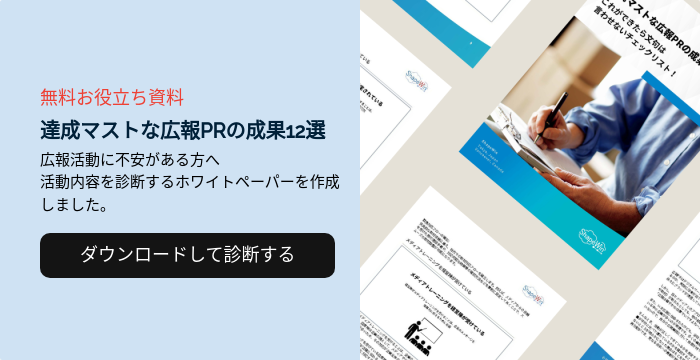「記者発表」と「記者会見」の違いが分かっていないという広報担当者も多いのではないでしょうか。
新商品や重要な情報を社会に発信する場面で、記者発表や記者会見の違いを理解し、正しく準備することは広報担当者にとって欠かせません。
本記事では、「記者発表とは何か」という基礎知識から、記者会見との違い、記者発表会を行うべきケースと具体的な流れまで、広報初心者にもわかりやすく解説します。
記者発表の意味と目的

そもそも、どういった広報活動を指して「記者発表」と呼ぶのでしょうか。
まずは「記者発表」の意味と目的を明確にし、その役割を理解するところから始めましょう。
▼広報の仕事の全体像はこちらの記事で解説しています。
広報の仕事とは?仕事内容や役割、必須のスキルまで徹底解説
記者発表とは
「記者発表」とは、企業や団体がメディアを通じて社会に向けて情報を発信する手段です。
新商品や新サービスのリリース、人事や組織変更、業績発表、提携や買収といった経営判断など、広く知ってもらいたい情報を社会に届けるために行います。
多くの場合は、プレスリリース(報道発表資料)の配信をもって記者発表と呼びます。
記者発表の目的は、情報の透明性を確保し、社会からの信頼を獲得することにあります。
特に報道関係者にとっては、企業の公式情報を得る貴重な機会となるため、正確で誠実な情報提供が求められます。
記者発表によって企業側は、自らの立場や見解を能動的に提示することができ、世間にポジティブな印象を残す効果も期待できます。
記者発表と記者会見の違い
「記者発表」と「記者会見」は、一見似ていますが、その性質や目的に明確な違いがあります。
まず、記者発表とは、企業が主にプレスリリースなどの文書を通じて、社会に対して情報を一方的に発信する手段を指します。特定の場やイベントを設けずに情報を配信することが多く、対話の機会は基本的にありません。
一方で記者会見は、主催者が記者を集めて開く、メディアとの「対話」が前提のイベントです。特に企業の経営に関わる重要な発表や社会的に注目度の高い事案において、記者の質問にその場で対応することが求められます。
「記者発表」は情報発信全体を指す広義の概念であり、その中に「記者発表会」や「記者会見」といった形式が含まれます。
関連記事:広報イベントをどうPRに繋げる?失敗しない開催方法
記者発表会の流れ・準備

記者発表会を成功させるには、綿密な準備と段取りが不可欠です。
ここでは、発表内容の整理から会場選び、リハーサル、当日の運営、アフターフォローまで、実務的な観点から流れを解説します。
①発表内容の明確化
まず重要なのは「何を発表するのか」を明確にすることです。
ニュースバリューがあるか、社会性があるか、ステークホルダーにとって重要な情報かどうかを精査しましょう。
経営陣と連携し、発表するべきテーマとその意義を言語化しておくことがポイントです。伝えたい情報が整理されていないと、当日の会見内容がぶれてしまい、メディアに正しく伝わらないリスクが生まれます。
②日時や場所の決定
次に、記者発表会の開催日時を決めます。
記者の参加を促すには、報道が集中しない曜日や時間帯を選ぶことが重要です。10時〜11時台、14時〜15時台など、記者が動きやすい時間帯が好まれます。
会場は、発表内容と関連性があり、写真や映像映えする場所が理想です。事前に下見を行い、照明・音響・撮影スペース・導線などを確認しておきましょう。
③企画書・リリースの作成と配信
発表内容が定まったら、企画書とプレスリリースを作成します。
企画書にはイベント概要、目的、登壇者、実施体制などを明記し、社内承認を得ます。
プレスリリースは、記者が記事にしやすい構成と表現を意識して、分かりやすくまとめましょう。
リリース配信は発表会の1-2週間前を目安にし、メディア各社へ事前告知を行います。PR TIMESなどのリリース配信サービスを活用することが一般的です。
関連記事:ニュースリリースとは?メディアに取り上げられる3つのポイントと書き方
④発表者や司会者の決定
次に、発表者や司会者を決めます。
発表者は経営層やプロジェクト責任者が務めることが多く、記者からの質問に対して信頼性のある回答をすることが求められます。
司会者は会の進行管理と時間配分、トラブル対応などを担うため、経験豊富なスタッフを配置しましょう。
当日の原稿や発言内容も準備し、事前にリハーサルを行うことが必要です。誤解を招く表現や数字のミスを避けるため、原稿は何度も確認を重ねましょう。
⑤メディアの誘致
メディアへのアプローチは広報の腕の見せ所です。
ターゲットメディアの選定、個別案内状の送付、電話でのアポイント取得などを通じて、当日の出席を促します。特にテレビや全国紙を誘致する場合は、企画の独自性や画作りの工夫が必要です。
また、SNSなどで発表会の告知を行い、情報の事前拡散も図ると良いでしょう。
関連記事:メディアプロモートとは?メディアとアポを取る3つのコツとアプローチ方法
⑥リハーサル
リハーサルは、成功への最重要プロセスです。
当日の流れに沿って、会場で実施しましょう。
プロジェクターや音響機器の動作確認、司会と登壇者の動線チェック、スライドの操作、質疑応答の想定質問など、細部に至るまで確認します。
特に質疑応答に備えた想定問答集(Q&A)は必須で、ネガティブな質問や鋭い切り口への備えもしておく必要があります。
▼当日のリハーサルの重要性・詳細はこちらの記事で詳しく解説しています
新商品発表会、いつから何をすべき?メディア掲載に繋げるポイントや開催方法も時系列で解説!
⑦実施
当日は、広報担当者が現場全体を指揮、監督します。
受付対応、進行、トラブル対応、メディアへの資料配布など、役割分担を明確にして運営しましょう。
記者との名刺交換や雑談も大切な仕事です。信頼関係を築くチャンスでもあるので、丁寧な対応を心がけましょう。
⑧フォローアップ
発表会後は、個別取材の対応や追加資料の提供など、フォローアップが必要です。
特にテレビ取材は当日よりも後日に設定されるケースが多いため、柔軟に対応しましょう。
報道された記事のクリッピング(収集)や社内共有、関係者への報告も忘れずに行います。メディア露出の効果測定や次回改善点の洗い出しにもつながります。
関連記事:メディアリレーションズとは?広報担当者のための用語解説
記者発表会が有効なケースと実施のポイント
すべてのニュースが記者発表会に適しているわけではありません。
ここでは、記者発表会が有効に機能する代表的なケースと、成功のポイントを解説します。
新商品・新サービスの発表

新商品や新サービスの発表は、記者発表会との親和性が非常に高いテーマです。
特に説明が必要なプロダクトや、デモンストレーションを通じて価値を訴求したい場合は、記者を招いて直接伝えることが有効です。
試供品の配布や実演展示を組み合わせることで、メディアの理解を促し、記事掲載率も高まります。SNSでの拡散も狙いやすいため、インフルエンサーを招待するのも効果的です。
人事や組織変更など経営に関する情報

トップ人事の発表や大規模な組織改編など、企業の方針や戦略転換に関わる情報も記者発表会に適しています。
記者が背景や意図を深く知りたがるテーマであるため、対話の場を設けて説明することが望ましいです。
また、経営陣のビジョンを直接語ってもらうことで、信頼感の醸成にもつながります。
危機管理

不祥事やトラブル発生時など、企業が厳しい局面にある場合も、記者発表会が有効です。
自主的に正確な情報を出し、誠実な姿勢を示すことでメディア対応の効率が上がります。
個別取材では質問が重複し、対応に追われがちですが、会見形式で一括対応すれば、共通回答で報道の精度を高めることができます。また、記者とのやり取りを通じて情報の誤解を防ぎ、火消しのスピードも速まります。
関連記事:失敗しないための危機管理広報マスターガイド!危機管理の基本から応用までを解説
まとめ:記者発表を通じて企業の信頼醸成を

記者発表や記者発表会は、企業が社会との信頼関係を築くうえで欠かせない広報活動の一つです。
特に、社会性の高いテーマや新たなサービス・製品の発表時には、記者発表会というリアルな場での発信が、報道の正確性とスピードを担保します。
一方で、発表内容の精査から会場手配、登壇者の調整、メディア誘致、さらには報道チェックに至るまで、実務の負担は決して軽くはないでしょう。
限られた時間と人員の中で、PR効果を最大化するには戦略的な設計と専門的な視点が欠かせません。
シェイプウィンでは、広報・PRの支援に加えて、SNSやSEOを活用した情報発信をサポートしています。広報・マーケティング戦略全体を見据えた記者発表のサポートが可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。