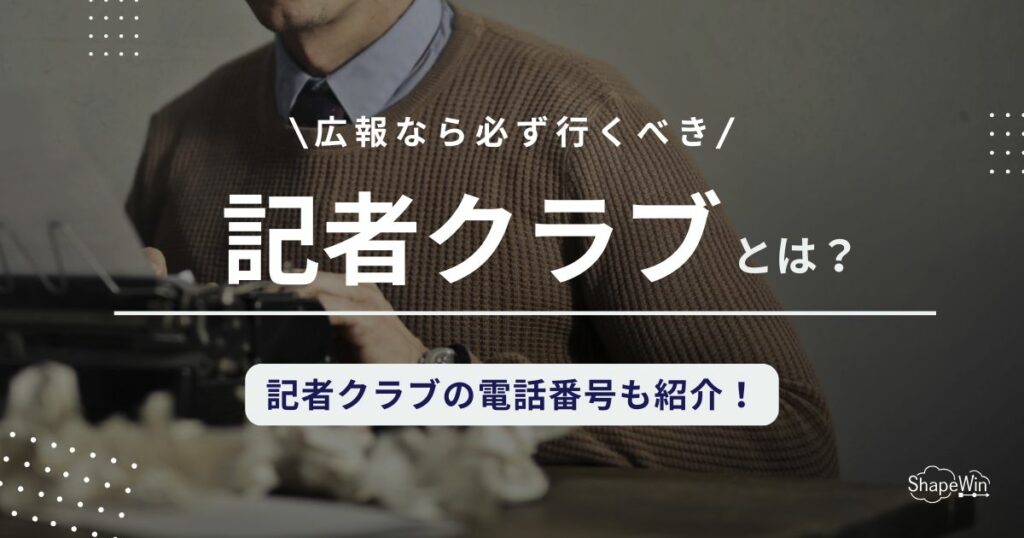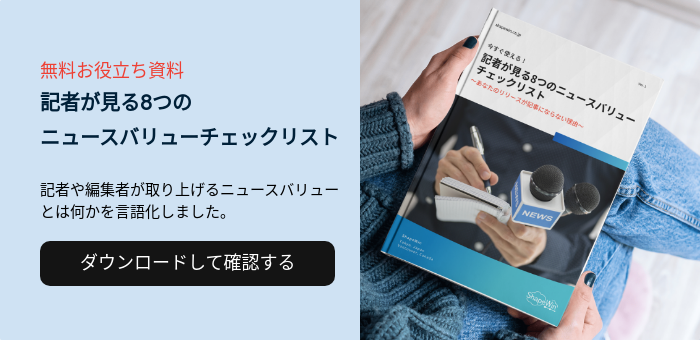「記者クラブにリリースを出すといいって聞いたけど、どうやって使えばいいの?」
「そもそも記者クラブって何?」
そんな疑問を抱えたまま、広報業務を任されていませんか。
記者クラブは、プレスリリースの配信先として機能する一方、情報開示ルールや申請手順など独自のルールや慣習も存在します。
本記事では、記者クラブの目的・仕組み・種類から、実務で使える投げ込みの手順、さらには注意点まで、広報担当者の実務に役立つ形で網羅的に解説します。
記者クラブとは?

広報やPR活動に携わると、一度は耳にする「記者クラブ」。名前は聞いたことがあっても、具体的な仕組みやルール、広報との関わり方まで理解している人は多くありません。
ここでは、まず「記者クラブとは何か」を基本から整理していきます。
記者クラブとは何か
「記者クラブ」とは、主に大手メディア(新聞社・通信社・テレビ局など)から派遣された記者が、特定の組織や分野を継続的に取材するために構成される団体を指します。海外のメディアが在籍する外国人記者クラブもあります。
日本の報道インフラの一つで、各省庁や地方自治体、経済団体などに設置されており、記者たちは記者クラブをベースに日々の報道活動を行います。
記者クラブの目的
記者クラブの目的は、大きく分けて二つあります。
一つは、報道各社の記者が取材拠点を共有することで、効率的かつ公平な情報収集を実現することです。
もう一つは、取材対象となる官公庁や団体との情報交換を円滑に行い、記者会見や資料配布を効率よく運用することで、迅速な報道が可能となることにあります。
記者クラブの種類

記者クラブは設置場所やテーマによって分類されており、目的に応じて適切なクラブに情報提供することが重要です。
以下に主な記者クラブの種類を整理しました。
業界・経済団体関連や、官公庁関連、政党関連の記者クラブに足を運ぶことは滅多にないと思いますが、特に広報として活用されやすいのは地方・府県記者クラブです。
| 種類 | 主なクラブ名 | 備考 |
|---|---|---|
| 業界・経済団体関連 | 兜倶楽部、金融記者クラブ(日銀クラブ) | 主に経済・金融系の報道を担当 |
| 官公庁関連 | 永田クラブ(内閣記者会)、霞クラブ | 政府や省庁の記者会見・発表の拠点 |
| 政党関連 | 平河クラブ、野党クラブ | 与野党それぞれに対応する専属組織 |
| 地方・府県 | 県庁記者クラブ(大阪、愛知、福岡など) | 地域密着型の情報発信に最適 |
業界・経済団体関連の記者クラブ
「兜倶楽部」や「金融記者クラブ(日銀クラブ)」などが該当します。
経済・金融系メディアの記者が常駐しており、証券・金融・マクロ経済に関する情報発信に適しています。上場企業の決算発表や金融政策関連のリリースなどはこのクラブに伝えます。
官公庁関連の記者クラブ
永田クラブ(内閣記者会)や霞クラブなど、各省庁に設置されているクラブです。
官房長官会見や各省の記者発表が行われる場として機能しており、政策発表や行政関連のニュースを届けたい場合にはここに投げ込みます。
政党関連の記者クラブ
政党の本部に設置されている平河クラブ(与党系)や野党クラブなどが該当します。
選挙、政局、法案に関する各党の状況や見解を報じる記者が常駐し、政治活動に関する発表をタイムリーに伝えるチャネルとして活用されます。
地方・府県記者クラブ
都道府県庁や政令指定都市などに設置された記者クラブです。
大阪、愛知、福岡など主要都市の県庁記者クラブは、地方紙や地域テレビ局の記者が常駐しており、地域に根ざした企業や行政機関の情報発信に特に効果的です。地方企業が地元メディアに取り上げられたい場合には、最初のステップとして機能することもあります。
広報活動のターゲットやリリース内容に応じて、適切なクラブを選ぶことが情報の到達精度を高める鍵です。
関連記事:記者クラブでプレスリリースのメディア露出を増やそう〜都庁記者クラブについて〜
記者クラブの電話番号一覧!
記者クラブへのプレスリリースの持ち込みや確認連絡の際には、クラブへの直接の連絡が必要です。
以下に、主な記者クラブの電話番号をまとめましたので、参考にしてください。
| 名称 | 電話番号 |
|---|---|
| 衆議院記者クラブ | 03-3581-0750 |
| 参議院記者会 | 03-3581-3111 |
| 経済研究会 | – |
| 法曹記者クラブ | 03-3592-7006 |
| 人事院記者クラブ | 03-3581-0651 |
| 財政記者会 | 03-3581-3728 |
| 財政クラブ | 03-3581-3731 |
| 国税庁記者クラブ | 03-3581-3676 |
| 文部科学記者会 | 03-5253-4111 |
| 厚生労働記者会 | 03-3595-2570 |
| 農政クラブ | 03-3591-6754 |
| 農林記者会 | 03-3501-3865 |
| 経済産業省ペンクラブ | 03-3501-1624 |
| 経済産業記者会 | 03-3501-1621 |
| 国土交通記者会 | 03-5253-8111 |
| 国土交通省交通運輸記者会 | 03-5253-8111 |
| 海上保安庁ペンクラブ | 03-3591-1803 |
| 科学記者会 | 03-5253-4111 |
| 総務省記者クラブ | 03-5253-5111 |
| 防衛記者会 | 03-5269-3271 |
| 環境省記者クラブ | 03-3580-3174 |
| 学術記者会 | 03-3403-1906 |
| 東京都庁記者クラブ | 03-5321-1111 |
| 労政記者クラブ | 03-3507-8485 |
| エネルギー記者会 | 03-5220-5650 |
| 自動車産業記者会 | 03-5405-6141 |
| 貿易記者会 | 03-3584-6546 |
| 農協記者クラブ | 03-5220-2552 |
| 金融記者クラブ | 03-3279-1111 |
| ラジオ・テレビ記者会 | 03-5455-2495 |
| 東京放送記者会 | 03-5455-2496 |
| レジャー記者クラブ事務局 | 03-6706-2106 |
| 日本旅行記者クラブ事務局 | 03-6706-2106 |
| スポーツ協会記者クラブ・JOC記者会 | 03-6910-5805 |
| 日本外国特派員協会<FCCJ> | 03-3211-3161 |
| 日本記者クラブ | 03-3503-2722 |
| ときわクラブ | 03-5334-0920 |
| 丸の内記者クラブ | 03-5334-0920 |
| 東商記者クラブ | 03-3283-7517 |
| 郵政記者クラブ | 03-3477-0111 |
| 大阪府政記者会 | 06-6941-0351 |
| 大阪労農記者クラブ | 06-6941-0351 |
| 大阪教育記者クラブ | 06-6941-0351 |
| 大阪府警内記者クラブ | 06-6943-1234 |
| 大阪市政記者クラブ | 06-6208-8181 |
| 大蔵記者クラブ | 06-6941-5331 |
| 司法記者クラブ | 06-6363-1281 |
| 青灯クラブ | 06-6376-6041 |
| 関西金融記者クラブ | 06-6206-7746 |
| 大阪証券記者クラブ | 06-4706-0988 |
| 大阪商工記者会 | 06-6944-1804 |
| 五月会 | 06-6441-8821 |
| 大阪機械記者クラブ | 06-6364-3641 |
| 大阪経済記者クラブ | 06-6944-6530 |
| 大阪科学・大学記者クラブ | 06-6443-5316 |
| 関西国際空港記者会 | 072-455-2201 |
| 近畿電鉄記者クラブ | 06-6341-1231 |
| 曽根崎警記者クラブ | 06-6315-1234 |
| 大阪建設記者クラブ | 06-6253-0071 |
| 関西レジャー記者クラブ | 06-6343-2290 |
| 兵庫県政記者クラブ | 078-362-3828 |
| 神戸市政記者クラブ | 078-322-5975 |
| 神戸民間放送記者クラブ | 078-322-5976 |
| 神戸経済記者クラブ | 078-303-5813 |
| 神戸海運記者クラブ | – |
| 京都府政記者クラブ | 075-414-4080 |
| 京都市政記者クラブ | 075-222-3200 |
| 京都経済記者クラブ | 075-353-7390 |
| 京都宗教記者会(西本願寺内) | 075-371-5181 |
| 京都宗教記者会(東本願寺内) | 075-371-9191 |
| 愛知県政記者クラブ | 052-961-2111 |
| 名古屋市政記者クラブ | 052-972-3355 |
| 県警記者クラブ | 052-951-1611 |
| 名古屋経済記者クラブ | – |
| 中部経済産業記者会 | 052-951-2563 |
| 名古屋証券記者クラブ | 052-251-1844 |
| 国税財務記者クラブ | 052-951-3511 |
| 名古屋司法記者クラブ | 052-201-8929 |
| 中部地方整備局記者クラブ | 052-953-8428 |
| 名古屋港記者クラブ | 052-654-7839 |
| 札幌市政記者クラブ | 011-211-3310 |
| 北海道道政記者クラブ | 011-251-6355 |
| 宮城県政記者クラブ | 022-211-3920 |
| 広島県政記者クラブ | 082-228-2111 |
※「広報・マスコミハンドブック(PR手帳)2025」の情報です
広報担当者が記者クラブを活用するメリット

広報活動の現場では、限られたリソースのなかでいかに効果的にメディア露出を獲得するかが常に問われます。その中で記者クラブは、情報を効率よく届けるためのチャネルとなり得るでしょう。
ここでは、広報担当者が知っておきたい記者クラブ活用の利点を紹介します。
①効率よくプレスリリースを投げ込める
記者クラブは、広報担当者にとって効率のよいプレスリリース配布先となります。
該当クラブに一度リリースを配布すれば、加盟している報道機関すべてに情報を届けることができるため、個別に記者へ送付する手間を大きく省略できるのです。
②自社の領域を担当している記者に情報を発信できる
クラブごとに記者の専門領域が決まっているため、自社の業界やテーマに適したクラブを選べば、最も関心の高い記者に情報が届きやすくなります。
たとえば、地方行政に関わるニュースや地方で行われるイベントなら地方・府県記者クラブが有効です。
関連記事:メディアに刺さるニュースバリュー:ニュースバリューの高め方を解説
知らないと危険!記者クラブのルールと注意点
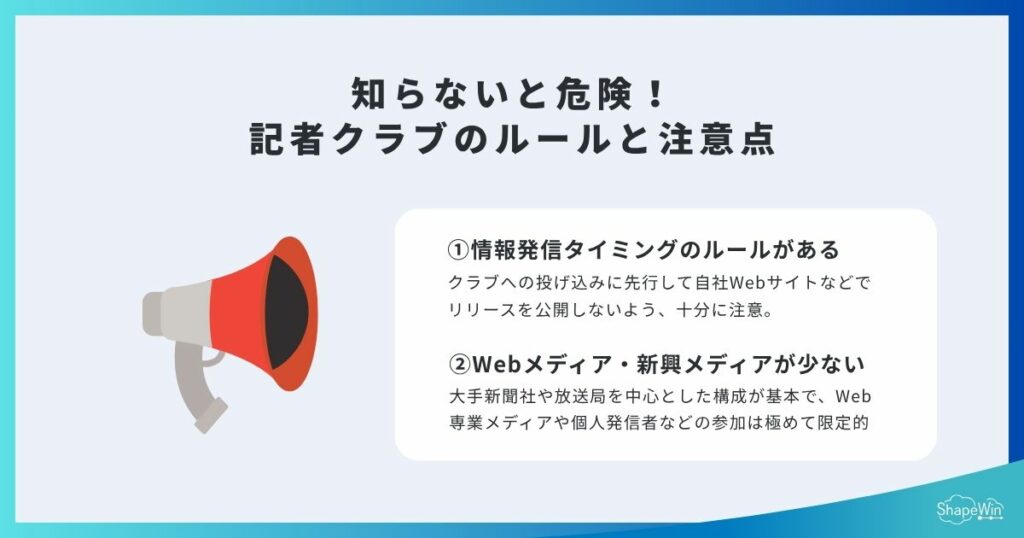
記者クラブは便利な情報発信の場である一方で、独自のルールや暗黙の了解が存在します。それらを知らずにリリースを配布してしまうと、意図せぬトラブルを招く可能性があります。
ここでは、広報担当者が注意すべき記者クラブ運用のルールやリスクについて解説します。
情報発信タイミングのルールがある
記者クラブでは、情報公開タイミングに関して「一斉・平等に解禁する」という原則が設けられています。クラブへの投げ込みに先行して自社Webサイトなどでリリースを公開しないよう、十分に注意しましょう。
Webメディア・新興メディアが非常に少ない
日本の記者クラブは長年、大手新聞社や放送局を中心とした構成が基本となっており、Web専業メディアや個人発信者などの参加は極めて限定的です。
そのため、広報戦略は記者クラブだけに依存せず、SNSやオウンドメディアなど他のチャネルとの併用が望まれます。
関連記事:メディアの種類を徹底比較!各メディアの強み・弱みとは?
記者クラブを活用しよう!投げ込みのやり方

実際に記者クラブを活用する際に欠かせないのが「投げ込み」と呼ばれるリリース配布の手続きです。これは単に用紙を持ち込むだけでなく、幹事会社との連携や期限厳守、配布形式などいくつかの段階があります。
ここでは、記者クラブでの投げ込みの基本的な流れと注意点について詳しく紹介します。
幹事会社を確認する
記者クラブへのリリース配布には、「幹事会社」への事前確認が必要です。
幹事会社は一定期間で入れ替わるため、まずは対象の記者クラブに電話をして、「今の幹事会社はどこか」「誰に連絡すればよいか」を確認し、連絡しましょう。
幹事会社からリリースの配布方法を聞く
幹事会社によって、リリースの受け渡し方法は異なります。以下のようなパターンがありますので、必ず事前に確認し、指定された形式・ルールに従いましょう。
また、本人確認のための名刺が2枚必要だったり、身分証明証の提示を求められることもありますので、事前に準備しておくと安心です。
・印刷物を直接持参(枚数指定あり)
・FAX送信
・指定のメールアドレス宛にPDF添付で送付
リリース提出の期限を守る
記者クラブによっては、リリース提出に期限があります。
たとえば総務省記者クラブでは、リリース配布希望の48時間前までに申請が必要という「48時間ルール」が設けられています。余裕を持ったスケジュール設計が欠かせません。
宣伝色を抑えたリリースを作成する
記者クラブでは「公的な情報発信」が原則とされています。
そのため、広告的・煽情的な表現は好まれません。事実ベースで構成し、客観性を意識した文体を心がけましょう。
関連記事:ニュースリリースとは?メディアに取り上げられる3つのポイントと書き方
加盟する全メディアに同じ情報を提供する
記者クラブは「情報の公平な共有」を重視しており、特定の会社だけに優遇情報を提供することはルール違反となります。全社に同一の情報を同時に提供することが求められます。
情報解禁の指定はNG
「この情報は〇月〇日〇時まで報道NGです」というような情報解禁指定は、原則として記者クラブでは受け入れられません。記者クラブでは、情報は即時共有されるという前提で進行します。
記者に個人的な売り込みはしない
クラブ内での記者との個人的なやりとりや売り込み行為は、暗黙のルールとしてNGとされています。記者の公平性や中立性を損なう行為とみなされるため、あくまで「オープンな場での情報提供」を基本姿勢としましょう。
まとめ:記者クラブを活用しつつ広報戦略の全体設計を

記者クラブは、広報やPR活動における「伝える力」を最大化するためのチャネルです。
プレスリリースを広く的確に届ける手段としては有効で、特に地域メディアとの接点が必要な企業にとっては活用するべき手段といえるでしょう。
一方で、ルールや手続きが煩雑であり、幹事会社とのやり取りや情報解禁のタイミング管理など、細かな配慮が必要です。また、記者クラブにリーチできたとしても、それだけで報道につながるとは限りません。
「記者クラブ」に関する知識は、広報担当者として知っておくべき基本ですが、それを単独でやりきるには限界があり、リソースや経験も求められます。
シェイプウィンでは、記者クラブ対応はもちろん、SNSやマーケティング、SEO、PRまで一貫して支援可能な体制を整えています。
無料相談も承っていますので、まずはお気軽にご相談ください。