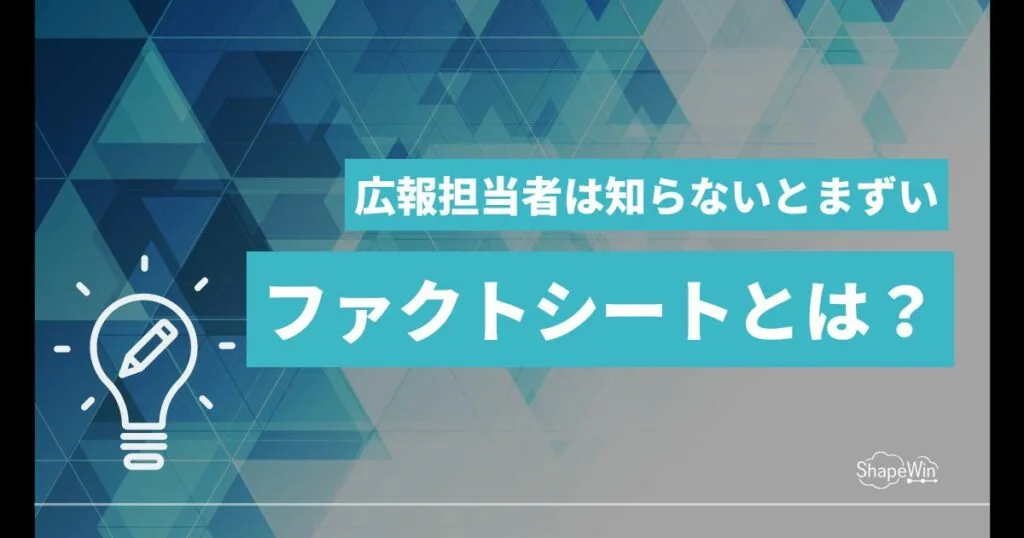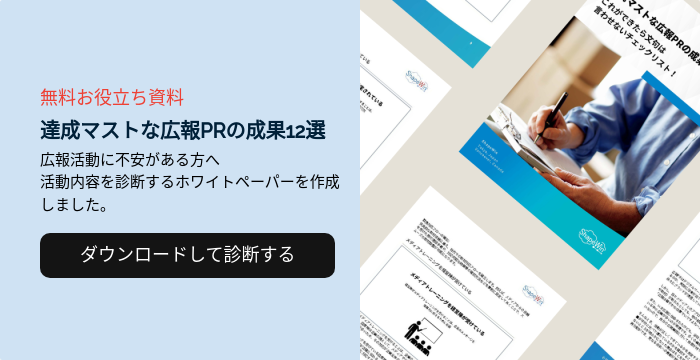企業が社会と信頼を築くには、数字や実績といった「事実=ファクト」をどう伝えるかがカギを握ります。特に広報がメディアにアプローチする際においては、単に事実を発信するだけではなく、根拠ある情報を開示することが不可欠です。
ファクトシートやファクトブックは、そうした情報を整理・開示するために必須のツールです。しかし、開示する項目や方法を誤ると、競合に有利な情報を渡してしまうなど、逆効果になるリスクもあります。
本記事では、ファクトシートの定義や用途、活用メリットから注意点、さらには実際の企業事例までを、PR視点でわかりやすく解説していきます。
ファクトシートとは?

ファクトシートとは、客観的な情報を簡潔にまとめた資料で、広報やIR、科学、行政などの分野で活用されています。
根拠のある数字やデータは、情報の信頼性を高め、第三者の理解と納得を促します。ファクトがあることで、単なる主観や意見に頼らず、読み手に「判断の材料」を提供できるのです。
ここでは、ファクトシートがどのような意味で用いられているかを整理します。
広報における意味
企業広報におけるファクトシート(またはファクトブック)は、会社概要、事業領域、提供サービス、業績推移、社会課題との関連性などをまとめたものを指します。
複数ページにわたる冊子形態で提供される場合は「ファクトブック」、1ページに収まるような要約資料は「ファクトシート」と呼ばれます。
たとえば、商品ラインごとにファクトシートを作成すれば、記者やメディアへの説明が格段にスムーズになります。
関連記事:メディアリレーションズとは?広報担当者のための用語解説
食品衛生分野における意味
食品安全委員会が作成するファクトシートは、国際機関や各国のリスク評価機関が発表した科学的データをもとに、危害要因ごとのリスク評価や管理措置を整理した概要書です。
これらの資料は、継続的に新しい研究結果や評価情報を収集・反映し、内容が常に最新の状態に保たれています。
そのため、行政機関や食品業界関係者、一般消費者にとっても、信頼性の高い判断材料として位置づけられています。
科学分野における意味
科学分野でのファクトシートは、製品・物質・技術などの特性、安全性、使用方法などを明確に伝えるためのツールです。
専門性の高いテーマでも、簡潔な文体でわかりやすく構成されている点が特徴です。
たとえば、新薬や化学物質に関する「安全な取り扱い方法」などが、一般消費者にもわかるように整理されています。
投資家向け広報(IR)における意味
投資家向け広報(Investor Relations)におけるファクトシートは、企業の成長戦略やビジョンを投資家に伝えるための基本資料です。
IR活動では、法律に基づく情報開示が求められる一方で、その情報の見せ方によって企業価値の伝わり方が大きく変わります。
たとえば、利益率の推移や事業ポートフォリオの変化、業界内でのポジションなどを数値で示すことで、単なる将来性の主張ではなく、根拠ある可能性として提示できます。
また、ファクトシートが整っていることで、投資家やメディアにとっての「判断材料」が増え、記者が記事を構成しやすくなったり、アナリストが企業の持つポテンシャルを正確に捉えやすくなるといった副次的な効果もあります。
関連記事:IR活動とは?具体的な活動内容と成功に導くポイントを解説
ファクトーシートを作成する3つのメリット

ファクトシートやファクトブックを持つことには、広報実務において多くの利点があります。
特にメディア対応や社内外への説明時に、明確で効率的な情報伝達が可能になります。
①取材のきっかけになる
広報担当者が記者に向けて情報を提供する際、ファクトシートがあることで記者の理解が深まりやすく、取材へのハードルが下がります。
数値や事実ベースの説明は、記者の「書きたい気持ち」を刺激するきっかけになります。結果として、自社に関する記事が増え、報道の精度も上がる可能性があります。
②情報の棚卸し・整理ができる
ファクトシートの作成プロセスは、社内情報の棚卸しそのものです。
どの情報が公開可能で、どの数字が強みになるのかを見極めることで、企業自身の理解も深まります。また、部門間の情報ギャップを埋める契機にもなります。
③記者が記事を書きやすくなる
取材において、記者は誤った情報発信をしないよう「事実確認」に多くの工数をかけます。
そのため、ファクトシートによってあらかじめ客観的な数値や定義等が整理されていれば、記者にとっては非常に扱いやすい情報となり、誤解や誤報のリスクも減らせます。
ファクトーシートの2つのデメリット

一方で、ファクトシートを運用する際には慎重さも必要です。
発信する情報の「見せ方」や「範囲」によっては、逆効果を招く可能性もあるためです。
①ファクトの開示によって不利になることがある
競合が公開していない数値を先んじて開示することで、思わぬ戦略上の不利を被ることがあります。
たとえば、シェア率や販売数、導入企業数などは業界内で比較対象となりやすく、過小に見えることでブランディング上の弱点となる可能性もあるのです。
開示する情報や開示先は慎重に判断しましょう。
②数字の見せ方が難しい
数字の「見せ方」は非常に重要です。
例えば、単に「100社に導入しました」と書かれていても、それがすごいことなのかどうか判断できません。「対象業界200社のうち、50%に導入されている」と、母数を表示したり数字の見せ方を工夫すると、価値や影響の大きさをより正確に伝えられます。コンテクストのない数字は、逆に誤解を招く恐れがあるため注意が必要です。
どの数字をどの文脈で使うのか、有効な発信方法を検討しましょう。
ファクトシートに載せるデータの例5選

ファクトシートやファクトブックの内容は、目的に応じて取捨選択することが重要です。
ここでは、特に掲載することが多い代表的な項目を解説します。
①社会課題の解決と絡めたデータ
自社が取り組む社会課題を明示することは、企業の存在意義や社会的信頼性を示す上で欠かせません。
たとえば、「労働生産性の低下」「医療人材の偏在」といった社会的な背景と、それに対して自社がどういうソリューションを提供しているかを示すことが重要です。
その根拠として、政府統計や第三者機関のレポートを引用すると、説得力が増します。
また、該当市場の規模や将来性のデータを添えることで、課題の重要性と事業の拡張性を同時に伝えることができます。
②業界のポジションがわかるデータ
自社のコアプロダクトがどのような特徴を持ち、業界の中でどのようなポジションにあるのかを示すことで、読み手の理解が深まります。競合製品との比較や、技術的優位性、独自の提供価値などを記載すると良いでしょう。
また、業界構造の中でどのポジションにいるのかを図解などで説明すれば、客観的かつ視覚的に理解されやすくなります。
③事業や商品別の売上高やシェアがわかるデータ
売上やシェアは、企業の成長性や市場でのポジションを示すうえで重要なデータです。特に事業や商品別の数字を明示することで、どの領域で強みがあるのか、どの分野に伸びしろがあるのかを伝えることができます。
ただし、業界全体の構造が不透明な場合や、大元のデータが取得しづらい市場においては、シェアを出すのが難しいこともあります。そのような場合には、自社内での売上構成比や前年比成長率など、代替となる指標を用いると効果的です。
重要なのは、数値の意味を明確にし、他のデータと組み合わせて「文脈のある情報」として提示することです。
④従業員数の推移がわかるデータ
企業の成長性や事業の安定性を示す材料として、従業員数の推移も有効です。特に採用や組織強化に積極的な企業であれば、「〇年連続で採用を強化」「管理部門から開発部門へ人材シフト」といった変化も読み手の関心を引くポイントになります。
可能であれば男女比や平均年齢、部門別人数なども示すことで、多様性や社風の特徴を補足できます。
⑤歴史や創業の経緯がわかるデータ
創業のストーリーや沿革は、企業の信頼性や共感形成に有効です。特にスタートアップ企業や中堅成長企業においては、「なぜこのビジネスを始めたのか」「どのような課題意識を持っているのか」といった背景が読者の記憶に残ります。
年表形式で沿革を紹介するほか、代表者コメントや創業当時のエピソードなどを添えると、より企業の人格が伝わるコンテンツになります。
ファクトシート作成のポイント4つ

ファクトを正しく伝えるには、単に「数字を並べる」だけでなく、信頼性や背景文脈を持たせる工夫が欠かせません。
作成のポイントを4つ紹介します。
①信頼できるデータを用いる
社内データだけでなく、公的機関の統計や業界団体の調査など、信頼性の高い出典を活用することが望まれます。
また、数値の変化には背景要因(外的要因と内的要因)を添えると、読み手の納得度が高まります。
②業界の構造やトレンドを伝える
自社視点での成功事例に留まらず、業界全体の動きやトレンドを客観的に伝えることで、説得力と信頼性が増します。
これにより、記者や投資家が「なぜ今このテーマを取り上げるべきか」を判断しやすくなります。
③ストーリー性のある発信をする
数字だけでは伝わらない「企業の想い」を、ストーリーとして加えることで読者の共感が得られます。
変化の背景や今後の展望を補足することで、単なる数字資料ではなく読み応えと説得力のあるファクトシートになります。
④開示目的を明確にする
何を誰に伝えたいのか、その目的を明確にしておくことが大前提です。
他社が開示しているからという理由だけで内容を真似するのではなく、自社にとって価値ある情報に絞って構成する必要があります。
ファクトシートを用いたPRの成功事例

BtoB領域では、ファクトシートやファクトブックの活用が企業の認知拡大や信頼構築に直結します。
特に無形サービスを扱う企業にとっては、「何を、どれだけ、どう貢献しているのか」を第三者に正確に伝えるための有力なツールとなります。
以下では、その代表的な成功例を紹介します。
調査リリースとファクトシートでメディア露出を実現
ヌーラボ社が行った調査リリースは、BtoB領域におけるファクトシート活用の成功例です。
同社は「チームワークマネジメント」という新たな概念を提示し、それに基づく定量調査を公開しました。市場に対する問題提起から始まり、自社の取り組みを客観的なデータで裏付け、その社会的意義をストーリーとして展開する構成は、非常に戦略的です。
このように、ファクトの蓄積と発信を通じて新たな市場カテゴリを定義することで、記者やメディアからの注目を集めやすくなります。調査結果が今起きている変化の証拠となれば、「今取り上げるべき企業」として認識されるきっかけとなるのです。
こうした調査リリースは、単発の話題性だけでなく、中長期的な広報・PR活動の基盤となるファクトシートとしても活用できるため、継続的なコンテンツ戦略として検討する価値があります。
まとめ:ファクトシートは企業の信頼を築くためのツール

ファクトシートやファクトブックは、企業にとって単なる「資料」ではなく、信頼構築の土台となる戦略的な広報ツールです。
メディアとの関係構築、IR活動、ブランド理解の促進など、あらゆるコミュニケーションの接点で有効に機能します。
一方で、データの出し方や構成を誤れば、企業の印象を損なうリスクを伴います。また、実際にファクトシートを作ろうとしても、リソース不足や社内連携の難しさ、複雑な情報設計といったハードルも存在するでしょう。
シェイプウィンでは、ファクトシートをはじめとする包括的な広報支援をワンストップで提供しています。
無料相談も承っていますので、まずはお気軽にご相談ください。