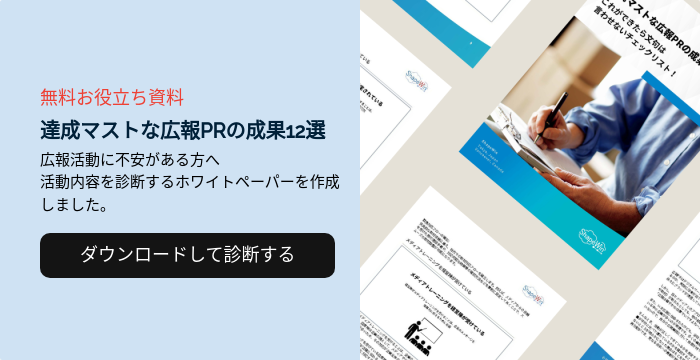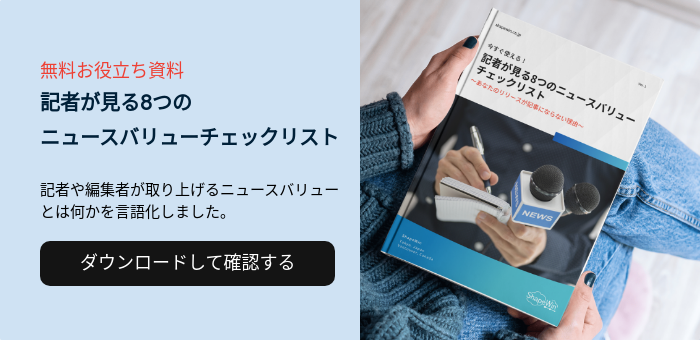「インフルエンサーマーケティングを実施したいけれど、本当に効果があるのかわからない」そんな悩みを抱えるマーケティング担当者も多いのではないでしょうか。
インフルエンサーマーケティングはSNS・PR施策として注目される一方で、売上やKPIとの結びつきが見えづらく、「なんとなく良さそう」で止まってしまうケースも少なくありません。
本記事では、インフルエンサーマーケティングの本来の役割をPR・マーケティング視点から整理し、効果を引き出すための設計ポイント、よくある失敗、そして効果測定の具体的な指標まで網羅的に解説します。
関連記事:PRとは?言葉の意味と6の活動内容、ポイント3つを徹底解説
インフルエンサーマーケティングの主な効果

まず押さえておきたい点は、インフルエンサーマーケティング施策は本質的には“PR”の一手法であるという点です。
売上に直結する販促ではなく、信頼や共感といった無形の価値を築くアプローチとして捉えることで、その効果の捉え方や設計も大きく変わります。
広告との違いや、SNS時代のユーザー心理を踏まえたメリットを理解すれば、インフルエンサー活用は単なる流行ではなく、ブランド認知や関係構築を目的とした戦略的なPR活動であることが見えてきます。
ここでは、マーケティング担当者が知っておきたい代表的な5つの効果をご紹介します。
①商品への信頼・安心感の向上
インフルエンサーマーケティングは、消費者にとって身近な存在であるインフルエンサー自身が商品を紹介するため、広告よりも信頼性が高く感じられます。
特に、自らの商品使用体験を語るレビュー形式の投稿は、ユーザー目線に立ったリアルな情報として受け取られ、「この人が使っているなら安心」といった心理が働きやすくなります。
また、フォロワーとインフルエンサーの間には一定の信頼関係が築かれており、その信頼の上に商品紹介が成り立っているため、ブランドや製品への安心感が醸成されるのです。
こうした効果は、特に新商品やまだ知名度の低いブランドにとって大きな後押しとなります。
②宣伝感が少なく、受け入れられやすい
従来の広告は「売り込まれる」という印象を与えてしまいがちですが、インフルエンサーマーケティングでは、製品やサービスがあくまで日常の一部として自然に登場するため、情報がスムーズに受け入れられやすくなります。
特にストーリーズや投稿内で「使ってみた」という文脈で紹介されると、宣伝というよりも「信頼できる人からのおすすめ」として認識されやすく、心理的な抵抗感を抑えることができます。
企業からのメッセージを、ユーザーのリアルな体験を通じて伝えられることこそが、広告にはないインフルエンサー施策の大きな強みです。
③ターゲティング精度が高い
インフルエンサーの多くは、特定のジャンルに特化したフォロワー層を持っています。
たとえば、美容系インフルエンサーであればコスメに関心の高いフォロワー、子育てインフルエンサーであれば主婦層が多く集まる傾向があります。
このため、商材とフォロワー層の親和性が高いインフルエンサーを選定することで、広告と比較して高精度なターゲティングが可能になります。
加えて、フォロワーの年齢層、居住地、興味関心といった属性も詳細に分析できるため、マーケティング施策としての再現性・効果測定も実施しやすくなります。精度の高いターゲットへの訴求は、無駄な広告費を削減し、ROIを高めるための重要な要素です。
④口コミ投稿・拡散につながる
インフルエンサーマーケティングの大きな強みの一つは、ユーザーによる口コミ(UGC:User Generated Content)を自然に生み出し、拡散できる点にあります。
インフルエンサーの投稿をきっかけに、フォロワーが「私も使ってみた」「これ気になる」といった形で自発的にSNS上で言及することで、さらなる波及効果が期待できます。
UGCは企業からの発信よりも第三者の声として受け取られるため、より強い説得力と影響力を持ちます。
さらに、投稿がシェア・リポストされることで、情報は二次的・三次的に拡散し、想定以上のリーチを得ることも珍しくありません。このような連鎖的な情報伝播は、広告では得難い拡散力です。
⑤オンライン販売で購入に繋がりやすい
インフルエンサーの投稿から、商品紹介ページやECサイトへのリンクを設置することで、興味を持ったユーザーがそのまま購買行動に移行しやすくなります。
特にInstagramやYouTubeなどでは、投稿からワンタップで購入ページに遷移できる導線が確立されているため、衝動的な購買を促進しやすい環境が整っています。
また、インフルエンサーの「実際に使ってみた」動画や使用感レビューは、購入を検討しているユーザーにとって大きな判断材料となります。購買までの心理的ハードルを下げ、スムーズな導線設計ができる点も、オンライン販売とインフルエンサーマーケティングの相性の良さを裏付けています。
インフルエンサーマーケティングのよくある失敗

インフルエンサーマーケティングはPR的な立ち位置で活用すべき手法であり、短期的な売上だけを追い求めると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。
ここでは、実際によくある失敗例を通じて、「なぜ効果が出なかったのか」「どうすれば避けられるのか」を明らかにし、今後の施策設計に役立つヒントを解説します。
インフルエンサーとうまく連携が取れていない
インフルエンサーは機械ではなく、自らの言葉やスタイルで情報を伝える「表現者」です。そのため、企業が一方的に情報を押し付けたり、テンプレート的な内容を指示したりすると、インフルエンサーの個性が発揮されず、フォロワーからも「不自然な投稿」として見抜かれてしまいます。
この失敗を防ぐには、事前のすり合わせが不可欠です。ブランドの価値観や目的を共有したうえで、インフルエンサーが自由に表現できる余白を持たせましょう。投稿内容については「コントロール」ではなく「共創」の意識が求められます。
施策が単発で終了する
インフルエンサーマーケティングでよくある失敗のひとつが、1回の投稿で売上アップを狙おうとするケースです。これは、テレビCMを一度流せば商品が売れるという誤ったイメージと近く、期待値の設定がそもそもズレていると言えるでしょう。
もちろん、商材によっては短期間でコンバージョンにつながることもありますが、それは例外的なケースにすぎません。施策の目的を売上に置きすぎると、全体の設計が不安定になり、成果に一貫性が生まれにくくなります。
SNSは情報の流れが速く、見逃されやすい媒体です。そのため、複数回の接触を前提とした継続的な露出が必要です。
本来、インフルエンサー施策はPRの一環として、中長期的に認知を広げたり、ブランドへの信頼を育てたりすることを目的とするべきです。インフルエンサーを、顧客との関係を築くスタート地点と捉え、長期的なコミュニケーションの中で活用していくことが成功の鍵になります。
インフルエンサーの選定がうまくいっていない
インフルエンサーマーケティングで成果が出ない典型例のひとつが、目的と異なるタイプのインフルエンサーを起用してしまうことです。
たとえば、認知拡大が目的なのにフォロワー数1万人以下のマイクロインフルエンサーを選ぶ、購入促進を狙っているのにライフスタイル重視のアカウントに依頼するなど、起用方針がずれているケースがあります。
インフルエンサーを選定する際は、目的や役割に応じて検討しましょう。
| 目的 | インフルエンサーの規模 |
|---|---|
| 認知拡大 | フォロワー数100万人以上の著名人(メガ) |
| ブランド構築 | ミドルインフルエンサー(数万〜数十万人) |
| UGC創出/購入促進 | マイクロ・ナノインフルエンサー(〜1万人) |
広告色が強くなる
複数のインフルエンサーに同時期に投稿を依頼した際、どの投稿も似たような構成・文言になってしまうことがあります。
このような状況では、フォロワーに違和感や飽きが生じ、コメント欄でも「案件っぽい」「またこの投稿か」といったネガティブな反応も見られます。
インフルエンサーマーケティングで重要なのは、ユーザーの共感を得ることです。
そのため、インフルエンサーに一律のマニュアルで投稿を依頼するのではなく、「それぞれのフォロワーにとって自然に映るか」を軸に設計することが重要です。
既存のユーザー・ファンから反発がある
すでに一定のファン層が存在するブランドの場合、ブランドの世界観と合わないインフルエンサーの起用や過剰なプロモーション演出は、かえってファンの期待を損ねてしまうリスクがあります。
ブランドの世界観とインフルエンサーの価値観が合っているかを事前に見極めることは、PR施策として非常に重要です。
「誰に届けるか」だけでなく、「誰から発信するか」も、ブランドにとっての資産であるという認識を持ちましょう。
効果測定はどう行う?代表的な指標

インフルエンサーマーケティングは、即時的な売上だけをKPIに置くと、その効果が正しく評価できません。
マーケティング施策である以上、効果測定も「認知」「態度変容」「関心喚起」など中長期的視点を含んだ複数の指標で捉えることが必要です。
ここでは代表的な3つの測定指標を紹介します。
①リーチ数・エンゲージメント率
認知獲得を目的とした施策においては、どれだけの人に情報が届いたか(リーチ数)と、どれだけの反応が得られたか(エンゲージメント率)が重要な指標になります。
InstagramやX(旧Twitter)などでは、「いいね」「保存」「コメント」「シェア」などの行動が数値化されており、投稿ごとの反響を比較することでユーザーの関心度を可視化できます。
施策の目的に応じて、注目すべき指標は次のように異なります。
・認知施策の場合:リーチ(情報が届いた人数)
・ブランディング目的の場合:エンゲージメント(いいね・保存・コメントなどの反応)
・販売・獲得目的の場合:コンバージョン(リンククリック、購入、問い合わせなど)
特にPR視点では、「接触した数」と「どれだけ関心を持たれたか」の両方を捉えることで、キャンペーンの浸透度やブランドとの親和性を測ることができます。リーチとエンゲージメントはセットで見るべき基本指標といえるでしょう。
②コンバージョンと売上につながる指標
インフルエンサーマーケティングが直接的な購買行動にどう影響したかを把握するには、CV(コンバージョン)に関する指標を追うことが有効です。特にECと連携した施策では、以下のような定量データを活用することで、広告との比較やROI分析がしやすくなります。
・投稿からのリンククリック数
・専用クーポンの使用数
・限定URL経由での購入件数
・ランディングページでのCVR(成約率)
ただし、これはあくまで施策の「一部」を評価する指標である点に注意が必要です。CVの数字が出なかった=効果がなかった、とは限りません。
リード獲得や関心層の可視化につながっている可能性もあるため、他の指標と組み合わせて全体像を評価しましょう。
③ブランドリフト調査
「認知は広がったが、企業イメージにどう影響したかまでは分からない」といった場合に有効なのが、ブランドリフト調査です。
これはインフルエンサー施策の前後で、ターゲット層に対してブランドに対する認知度・好意度・購入意向などを定量調査し、変化を比較する手法です。
特にPR視点でのインフルエンサーマーケティングでは、「知っていたか」「どう感じたか」「買いたくなったか」といった態度変容を捉えることが重要です。短期的なCVでは見えない施策の価値を定量化できる点で、広告評価とのバランスを取る補完的な指標として注目されています。
インフルエンサーマーケティングはこんな企業におすすめ

インフルエンサーマーケティングは、すべての企業に効果的というわけではありません。
SNSを活用したPR・ブランディング手法である以上、「誰に」「何を伝えたいか」によって向き・不向きがあります。
ここでは、特に相性が良く、成果が出やすい企業の特徴を3つ紹介します。
①若年層向け商材を扱っている
インフルエンサーマーケティングは、SNSネイティブである10〜30代の若年層に強い影響力を持ちます。
InstagramやTikTok、YouTubeなどで情報を得ている世代にとって、インフルエンサーの発信は「広告」ではなく「信頼できる口コミ」として受け取られる傾向があります。
たとえば、コスメ、ファッション、ライフスタイル雑貨、飲食チェーン、サブスクサービスなどは、実際に使った感想や見た目の印象が重要視されるため、インフルエンサーの体験型コンテンツとの親和性が非常に高いといえます。
関連記事:インフルエンサーマーケティングとミレニアル・Z世代(アメリカの調査結果)
②ブランディングに課題を感じている
「サービスは良いのに魅力がうまく伝わらない」「知名度が低くて検討の土俵に上がれない」といった悩みを抱える企業にとって、インフルエンサーの力を借りたストーリーテリングは有効な手段になります。
インフルエンサーがブランドの価値や背景を、自分の言葉で気持ちを込めて伝えることで、無機質な企業情報では届きにくい層にも想いを届けることができます。
たとえば、あるメーカーではCSR活動として行っていたリサイクルの取り組みをインフルエンサーに紹介してもらうことで、「環境に配慮している会社」というブランドイメージを醸成しました。
このように、PRの本質である「ストーリーを伝えること」と、インフルエンサー活用は非常に親和性が高いのです。
また、商談や営業活動においても「このブランド、YouTuberの○○が紹介してたよね」といった話題が生まれやすく、企業の信用力や興味喚起にも寄与します。
関連記事:マーケティングコミュニケーションの手法は?戦略で成功した事例も紹介!
③Web広告の効率が落ちてきたと感じている
近年、多くの企業が直面しているのが「Web広告のCPAが上がってきた」「バナーを出しても反応が取れない」といった課題です。
特に若年層は広告離れが進んでおり、従来型のディスプレイ広告やリスティング広告だけでは接点を持ちにくくなっています。
このような背景から、Web広告の補完施策としてインフルエンサーマーケティングを導入する企業が増えています。自然な投稿スタイルやコンテンツの親しみやすさによって、広告では届かない潜在層にリーチできる点が大きな魅力です。
まとめ:インフルエンサーマーケティングにはPRの視点が重要

インフルエンサーマーケティングは、認知拡大やブランディング、共感形成といったPR的効果を持つ、今の時代に欠かせないマーケティング手法です。
商品の信頼性や魅力を自然なかたちで届けられる反面、施策設計や効果測定を誤ると「効果がない」と誤解されてしまうリスクもあります。
だからこそ、ターゲットに合わせた戦略設計やKPI設定、適切なインフルエンサー選定などが重要です。
しかし、インフルエンサー施策を単独で実施しても、全体のPR・マーケティング戦略と連携していなければ、本来の力を十分に発揮することは難しいでしょう。加えて、日々変わるSNSアルゴリズムやユーザーの行動変化、複雑化する施策評価など、多忙な現場でそれらすべてに対応するのは容易ではありません。
シェイプウィンでは、SNS、マーケティング、SEO、PRを含む幅広い視点から、インフルエンサーマーケティングを成功へと導く支援を行っています。
戦略設計からコンテンツ制作、最適なインフルエンサーの提案までワンストップで対応可能です。
まずはお気軽にご相談ください。