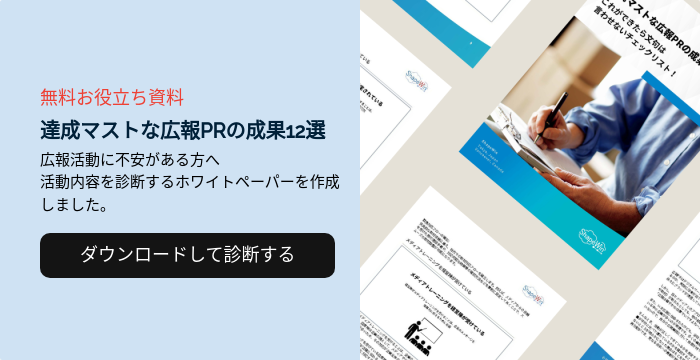「オウンドメディアで記事を公開しているのに閲覧数が伸びない」
「オウンドメディアとSNSを、どう連携させれば効果的なのかわからない」
このような悩みをお持ちのマーケティング担当者や広報担当者は多いのではないでしょうか。デジタルマーケティング戦略の要となるオウンドメディアとSNSの連携は、企業のブランド構築と顧客獲得における重要な課題です。
本記事では、オウンドメディアとSNSの効果的な連携方法と集客につなげるためのポイント、そして陥りがちな失敗とその対策を解説します。
※この記事では、オウンドメディアとは自社ドメイン配下のブログやコラムなど、自社が保有・運営するWebサイトを指します。
オウンドメディアとSNSの違い
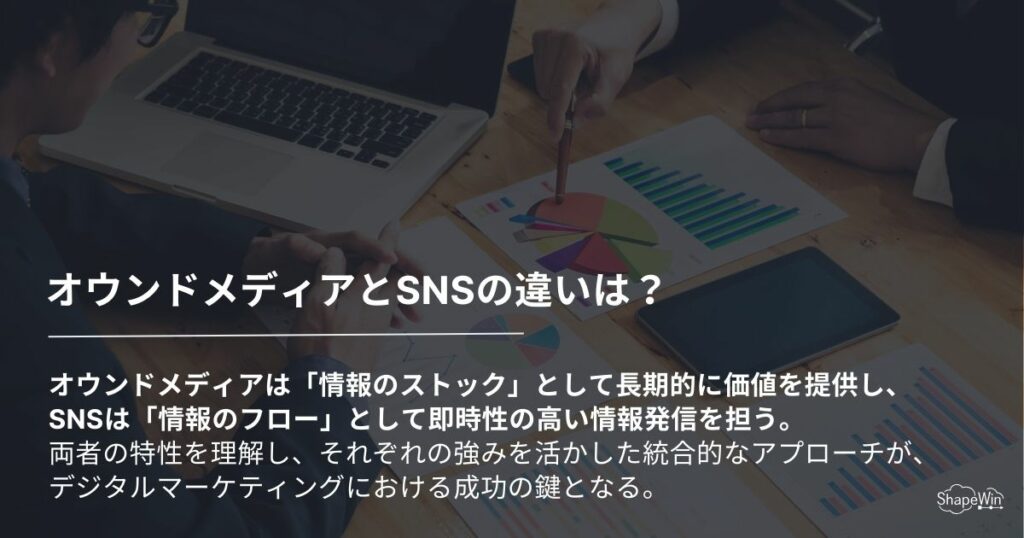
オウンドメディアとSNSは、それぞれ異なる特性を持ちながらも、相互に補完し合う関係にあります。
オウンドメディアは「情報のストック」として長期的に価値を提供し、SNSは「情報のフロー」として即時性の高い情報発信を担います。
両者の特性を理解し、それぞれの強みを活かした統合的なアプローチが、デジタルマーケティングにおける成功の鍵となります。
まずは、両者の具体的な違いを見てみましょう。
| 項目 | オウンドメディア | SNS |
| 目的 | 情報の蓄積・専門性の発信・SEOによる集客 | 認知拡大・エンゲージメント向上 |
| 流入経路 | 検索(能動的なアクセスによる) | フォロワー、シェア、バズなど(受動的な接触が多い) |
| コンテンツの寿命 | 長期的 | 短期的 |
| 資産性 | 高い(自社管理) | 低い(プラットフォーム依存) |
| 情報の深さ | 深い(詳細・専門的な内容) | 浅い(簡潔・視覚的な内容) |
| 更新頻度 | 週1回〜月数回 | 毎日〜週数回 |
これらの特性を理解した上で、両メディアを効果的に連携させることが重要です。
なぜオウンドメディアとSNSの連携が必要なのか?

オウンドメディアとSNSの連携は、単なるオプションではなく、効果的なデジタルマーケティング戦略の必須要素です。そのメリットを5つ紹介します。
①記事公開直後でも認知獲得が可能
オウンドメディアの新規記事は、公開直後はSEOの効果が現れにくいという課題がありますが、SNSと連携することで、初期段階での認知獲得と流入増加が可能になります。
たとえば、新しく公開した記事の要点やハイライトをSNSで共有することで、即時的な閲覧者を獲得できます。特にX(旧Twitter)やLinkedInでの専門的な内容の共有は、ビジネスパーソンからの注目を集めやすいでしょう。
具体的な方法としては、記事のキーメッセージを抽出し、簡潔な文章とともに記事URLを共有します。画像や引用なども添えることで、クリック率を高めることができます。また、複数回に分けて異なる切り口でシェアすることも効果的です。
初期流入の増加は、その後のSEO評価にも良い影響を与える可能性があります。
②オウンドメディアの運用初期でも流入が見込める
オウンドメディアを立ち上げたばかりの段階では、ドメインパワーが弱く、SEO効果が出るまでに時間がかかります。競合が多い市場では特に、オーガニック検索での上位表示を獲得するまでの期間が長くなりがちです。
この段階でSNSを活用することで、サイト認知の向上と流入獲得が可能になります。
具体的には、オウンドメディアのコンセプトや内容をSNSで紹介したり、記事更新の告知を定期的に行ったりすることで、徐々にフォロワーやサイト訪問者を増やしていきます。
また、業界のインフルエンサーやコミュニティとの関係構築も重要です。関連するハッシュタグを活用し、業界のディスカッションに参加することで、専門性をアピールできます。
③集客の相乗効果が見込める
オウンドメディアの専門性とSNSの拡散力が組み合わさることで、以下のような相乗効果が生まれ、効果的な集客が実現します。
ただし、この相乗効果は自然に生まれるものではありません。SNSのアルゴリズムはコンスタントに変化し、オーガニックリーチが減少傾向にあります。
「オウンドメディアの記事をSNSでシェアすれば自然に拡散される」という理想的なケースは稀です。
効果的な連携のためには、単なる記事リンクの共有ではなく、SNSの特性に合わせたコンテンツ加工(視覚的要素の強化、簡潔なメッセージングなど)が重要です。
また、適切なタイミングと頻度での投稿、ユーザーの反応分析なども欠かせません。
④ユーザーの声をオウンドメディアに生かせる
SNSによって集めた顧客の声や市場のニーズを、オウンドメディアのコンテンツ企画に活かすこともできます。
SNSではリアルタイムでユーザーの反応を把握できるので、特定の投稿に対する反応が良かった場合、それをオウンドメディアの記事テーマとして発展させることができます。
また、SNSのQ&Aやアンケート機能を活用して、ユーザーの疑問点や課題を直接調査し、それをオウンドメディアでの解説記事として展開する方法も効果的です。
実際にユーザーが抱える疑問や関心事に基づいたコンテンツは、より高い共感を得られ、価値の高いオウンドメディアの記事制作に繋がります。
⑤SEO依存のリスクを分散できる
検索エンジンのアルゴリズム変更に左右されない集客チャネルを確保できる点も、大きなメリットの一つです。
SEOに依存したオウンドメディア戦略は、検索エンジンのアルゴリズム更新によって影響を受ける可能性があります。実際にGoogleではアルゴリズム更新が頻繁に行われ、SEOへ与える影響も大きくなっています。
オウンドメディアとSNSを並用することで、SEO依存のリスクを分散させることができます。
また、特定のキーワードで検索上位を獲得するのが難しい競争の激しい分野でも、SNSを通じて直接的にターゲットへリーチすることが可能です。これはドメインパワーが弱い段階での重要な戦略となります。
オウンドメディアとSNSの連携による集客戦略

オウンドメディアとSNSを効果的に連携させるには、単なる記事のシェアだけでなく、戦略的なアプローチが必要です。
そのためには、各SNSプラットフォームの特性を理解し、ターゲットに合わせた展開が重要になります。ここでは、具体的な6つの戦略を解説します。
①ターゲットに応じたSNSの選定
効果的なSNS活用の第一歩は、ターゲットに最適なプラットフォームを選ぶことです。
各SNSの利用者層や特性は、以下のように明確に分かれています。
・X(旧Twitter)
ビジネス・テクノロジー・金融関連のトピックに強く、B2Bマーケティングや専門的な情報発信に適しています。簡潔で引用可能な専門的知見、業界ニュースのコメントなどが効果的です。
・LinkedIn
ビジネスプロフェッショナル向けのプラットフォームです。B2Bマーケティングに最適で、業界インサイト、企業文化、リーダーシップに関するコンテンツが評価されます。業務提携や人材採用にも活用できます。
・Instagram
ビジュアル重視のため、製品やサービスのビジュアル表現、企業カルチャーの紹介などに適しています。特に若年層への訴求力が高いのが特徴です。
関連記事:【インスタSEO】5つのポイントとエンゲージメントを高めるコツ
・TikTok
短尺動画プラットフォームです。若年層向けの親しみやすいコンテンツや教育コンテンツが強みですが、専門知識を簡潔に解説する動画なども効果的です。
・Facebook
コミュニティ形成やイベント告知、詳細なコンテンツ共有に適しています。30代以上のユーザーへのリーチに効果的です。
SNS選定では、業界特性も考慮する必要があります。たとえば、B2B企業であればLinkedInとXを中心に、消費者向け製品であればInstagramやTikTokを重視するなど、ターゲットとする顧客層に合わせた選択が重要です。
②拡散を狙う投稿テクニックの活用
SNSでの拡散力を高めるには、各プラットフォームの特性を理解した投稿のテクニックが必要です。
ユーザーの行動パターンやプラットフォームの特性を把握し、以下のような点に留意しましょう。
・投稿時間帯と頻度の最適化
一般的に、平日の朝7-9時、昼12-13時、夕方17-19時頃がエンゲージメント率の高い時間帯とされています。
また、LinkedInではビジネスアワー内、InstagramやTikTokでは夕方から夜にかけての投稿が効果的です。
投稿頻度も、各プラットフォームによって最適な回数が異なります。
・X :1日2-5回
・LinkedIn :1日1-2回
・Instagram:1日1回程度
・Facebook:1日1回程度
・コメント欄の活用
投稿の本文にURLを含めると、一部のプラットフォームではリーチが制限される場合があります。そのため、特にFacebookやInstagramでは、最初のコメントにURLを記載する手法が有効です。
また、コメント欄での質問投げかけやユーザーとの積極的なやりとりも、エンゲージメントを高める重要な要素です。
・シェアされやすいタイトルの工夫
SNS投稿用のタイトルは、SEO向けのタイトルとは異なるアプローチが必要です。
数字を含める(「5つの方法」など)、質問形式にする、意外性のある表現を使う、感情に訴えかけるなどの工夫が効果的です。
・目を引く画像・動画の使用
視覚的要素は拡散力に大きく影響します。オリジナルのグラフィック、インフォグラフィック、ブランドカラーを活用した画像などが効果的です。
また、各プラットフォームの推奨サイズに合わせた画像設定も重要です。
これらのテクニックを組み合わせ、継続的に検証・改善していくことで、SNSでの拡散力を高めることができます。
関連記事:企業SNS運用の成功法則!効果を最大化する戦略とは?
③外部の人が関わったコンテンツを作る
外部の人物を巻き込んだコンテンツは、SNSでの拡散力を高めるだけでなく、投稿の信頼性ももたらします。特にインタビュー対象者は、自分が関わった記事を自発的に共有する傾向があるため、自然な拡散につながります。
効果的な外部連携の方法には、このようなものがあります。
・業界専門家インタビュー
専門家や影響力のある人物へのインタビューは、その人のネットワークにリーチできるだけでなく、コンテンツの信頼性も高めます。
インタビュイーには、記事公開時にSNSでの共有を依頼しましょう。
・パートナー企業との協業
ホワイトペーパーやウェビナーなどの共同制作は、双方のネットワークを活用した効率的な拡散が可能です。両社の専門性を組み合わせることで、より価値の高いコンテンツが生まれます。
・社内専門家の活用
自社社員の専門知識を活かしたコンテンツも効果的です。社員自身のSNSアカウントからの共有を促すことで、個人のプロフェッショナルネットワークにリーチできます。
外部関係者との協業では、共有方法のガイドラインや投稿テンプレートを用意しておくと、より効果的な拡散が期待できます。タグ付けやハッシュタグの使用方法も、忘れずに提案しましょう。
④SNS発信のリスクを理解しておく
SNSの大きな特徴は、一度発信した情報のコントロールが難しいという点です。
情報は予想以上の速さで拡散し、発信者の意図とは異なる文脈で解釈されることもあります。
情報が部分的に切り取られて拡散されるリスクや、炎上が急速に拡大する恐れ、発信者の意図と異なる解釈をされるリスクに対応するためには、投稿前のチェックと危機管理対応の体制構築が不可欠です。
そして、最も重要なのは、コントロールを目指すのではなく「対話」を重視する姿勢です。否定的なコメントも含めて真摯に対応し、透明性のあるコミュニケーションを心がけることで、むしろ信頼構築のチャンスとなります。企業アカウントにも「人間らしさ」が求められる時代なのです。
⑤オウンドメディアのコンテンツを二次活用する
一つのオウンドメディア記事から複数のSNS投稿を生み出すことで、効率的な情報発信が可能になります。
長文記事の転用方法としては、インフォグラフィック、引用画像、スライドカルーセルなどのビジュアルコンテンツへの変換や、記事の要点を凝縮した短尺動画の作成が効果的です。
また、LinkedInでは専門的な洞察、Instagramではビジュアルコンテンツというように、各SNSの特性に合わせた最適化も重要です。
このようなコンテンツ派生の取り組みは、初期段階では労力を要しますが、テンプレート化やワークフローの確立によって、大幅な効率化を図ることができます。
⑥社内の人に協力してもらう
社内リソースを活用したSNS拡散は、コストをかけずに効果を高められる重要な戦略です。企業アカウントよりも社員の個人アカウントからの発信の方が、エンゲージメント率が高い傾向があります。
効果的な社内連携体制を構築するには、社内SNSガイドラインの作成、簡単に使えるシェアテンプレートの提供、そして社員のSNS活用を支援する研修が有効です。
特に、経営層や各分野の専門家の個人アカウントからの発信は大きな影響力を持ちます。
こうした取り組みは、単なる情報拡散にとどまらず、社員のエンゲージメント向上や企業文化の強化にも寄与するでしょう。
SNS活用でよくある失敗と対策

オウンドメディアとSNSの連携において、多くの企業が共通して陥りがちな失敗があります。
ここでは、代表的な3つの失敗パターンとその対策を解説します。
SNSの発信のみに偏ってしまう
SNSの即時性や拡散力に魅力を感じ、SNSだけで情報発信を完結させようとする企業は少なくありません。
しかし、この手法には、以下のように多くのリスクが潜んでいます。
・プラットフォームの規約変更やアルゴリズム変更に左右される
・ユーザーの行動データや分析の範囲が限定される
・過去のコンテンツが埋もれてしまい、長期的な価値を生み出せない
・プラットフォームがサービス終了した場合に、コンテンツ資産が失われる
こうしたリスクを避けるためにも、SNSは「集客・対話の入口」、オウンドメディアは「詳細な情報提供・コンバージョンの場」と位置づけ、相互補完的に運用しましょう。
フォロワー数のみをKPIにしてしまう
多くの企業がSNS運用において「フォロワー数」を重視しますが、これは表面的な指標に過ぎません。
関心の薄いフォロワーが多いとエンゲージメント率が下がりますし、フォロワー数の増加が集客の増加に直結しない場合も少なくありません。
効果的なSNS運用のためには、ビジネスの目標に直結した複合的なKPI設定が重要です。
エンゲージメント率(反応の割合)、クリック率(オウンドメディアへの誘導成功率)、コンバージョン率(問い合わせなどにつながった割合)、リーチの質(ターゲット層へのリーチ度合い)、コンテンツの共有率などを組み合わせて総合的に評価しましょう。
定期的な分析・改善と共に、「会話の質」や「コミュニティ形成」といった定性的な側面も重視することが成功への鍵です。
投稿の一貫性がない
多くの企業が陥りがちな失敗の一つが、SNS投稿の一貫性の欠如です。
担当者や投稿時期によって、投稿のトーン・ビジュアルやメッセージの方向性が変わると、ブランドの一貫したイメージが構築できなくなり、企業に対する安心感や信頼感を損ねることにも繋がります。
効果的なSNS運用のためには、明確なコンセプト設計が重要です。
まずは、コミュニケーション方針、コンテンツピラー(3-5つの主要テーマ)、ビジュアルガイドライン、投稿スケジュール、対応ガイドラインなどを事前に策定しましょう。
そして、これらを文書化した「SNSガイドライン」を作成し、関係者全員で共有することで、一貫性のある効果的なSNS運用が実現します。
SNSでオウンドメディア集客に成功した事例

実践例を見ることで、オウンドメディアとSNSの効果的な連携についての理解が深まります。
ここでは、SNSとオウンドメディアの活用に成功した事例を紹介し、その戦略から学べるポイントを解説します。
LIG
Webソリューションを提供する株式会社LIGは、オウンドメディアとSNSの連携で成功した代表的な事例です。
LIGのオウンドメディアとSNSから学べる最大のポイントは、「専門性の高いコンテンツをいかに親しみやすく伝えるか」という点です。
技術的な内容でも、実践的で読者の課題解決に直結する形で提供することで、SNSでも共有されやすく、オウンドメディアへの流入増加につながっています。
また、社員一人ひとりが自身の専門分野の「顔」となって情報発信する文化も注目すべき点です。個人のネットワークを活用した自然な拡散は、特に専門性の高い分野で効果を発揮します。
クラシル
料理レシピアプリ「クラシル」を運営するdely社も、オウンドメディアとSNSの連携による成功事例として注目されています。
成功要因としては、以下の点が挙げられます。
・短時間で完結する料理動画が、特にInstagramやTikTokでシェアを促進したこと
・各プラットフォームに合わせて最適化された投稿戦略
・季節イベントや食のトレンドに沿った投稿による定期的な話題創出
クラシルから学べる重要なポイントは、「コンテンツの再利用と最適化」です。一つのレシピ(コンテンツ)を様々な形に加工し、各SNSプラットフォームの特性に合わせて発信することで、効率的かつ効果的な情報発信を実現しています。
また、SNSでユーザー参加型のコンテンツを促進し、それをオウンドメディアで取り上げるという循環を生み出している点にも注目です。これにより、SNSでの拡散とオウンドメディアへの流入という双方向の効果を最大化しています。
まとめ:自社メディアの相乗効果が顧客獲得とブランド構築の鍵となる

オウンドメディアとSNSの効果的な連携は、企業のブランド構築と顧客獲得の重要な戦略です。
効果的な連携のためには、ターゲットを明確にしたSNS選定や、各プラットフォームの特性に合わせたコンテンツの最適化、統一感のあるコミュニケーション戦略が不可欠ですが、真の課題は、これらを継続的に実行することでしょう。
多くの企業は日々の業務に追われ、戦略的なメディア運用が後回しになりがちです。
オウンドメディアやSNS運用といえば、日本では広告代理店が支援を行うイメージが強いですが、企業広報との連携の必要性から、世界ではPR会社が支援することが通常です。
シェイプウィンは、日本では数少ないオウンドメディア運用を支援するPR会社として、戦略企画からメディアリレーション、オウンドメディア構築、SNS運用、SEO対策まで包括的なサポートを提供しています。
無料相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。